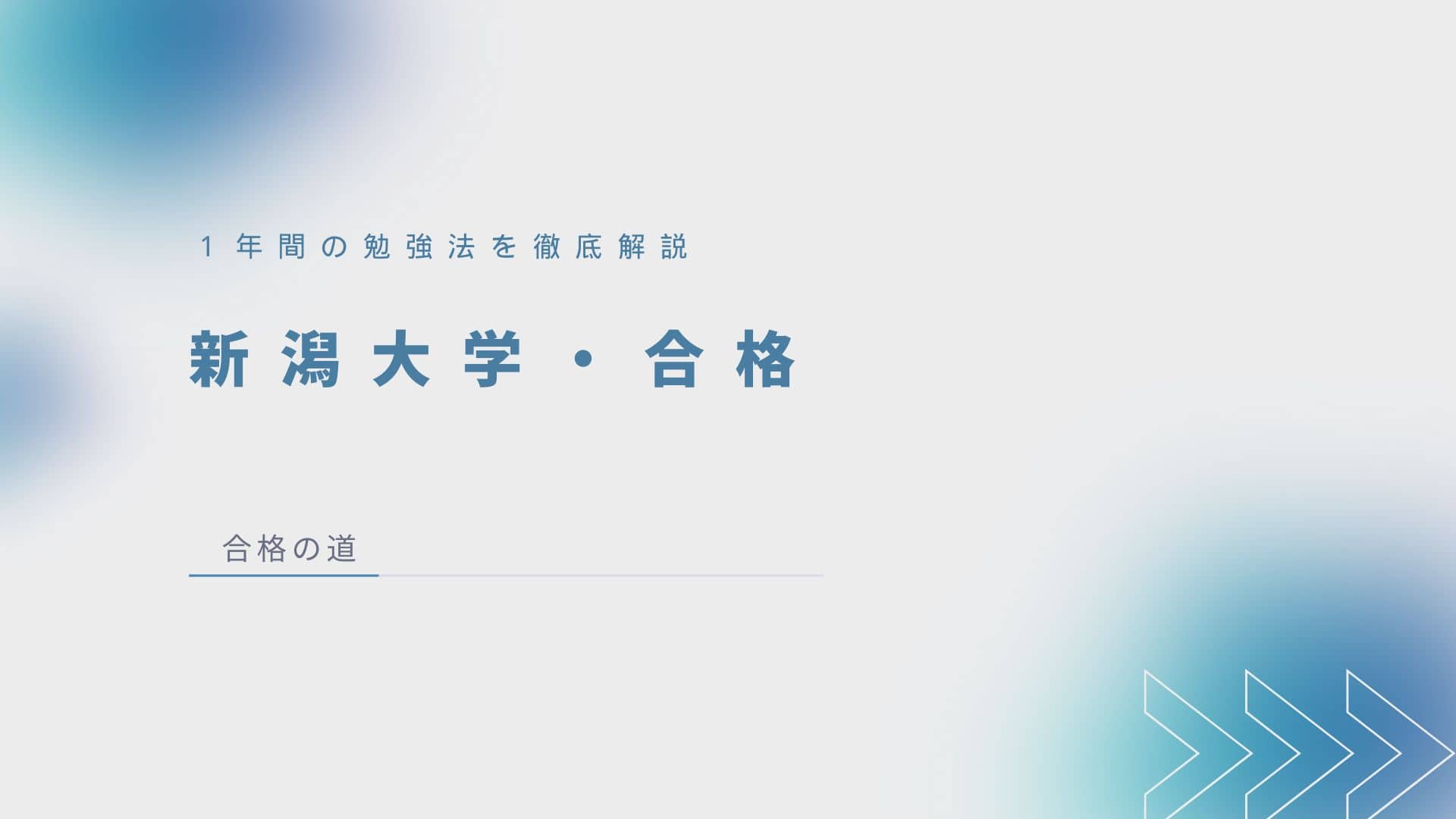
目次
新潟大学勉強法とは何でしょうか。
そこで、本記事では1年間の勉強計画を季節ごとに分けて解説します。
つまり、ただ勉強するだけでなく、 「いつ何を学ぶか」が重要です。
さらに、模試や過去問の活用法も紹介します。
したがって、新潟大学を目指す人は、この勉強法を参考にしてください。
そして、合格に向けて無駄のない勉強を始めましょう。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
ホームページ:新潟大学
新潟大学の入試を知ることが合格の第一歩
まずは入試制度を正しく 理解しよう
新潟大学では、以下の選抜方式があります。
- 一般選抜(前期・後期)
- 推薦型選抜(学校推薦型・公募推薦)
- 総合型選抜(旧AO入試)
👉 つまり、自分がどの方式で出願するのかを早めに決めることが戦略の第一歩です。
次に共通テストの配点と目標点を確認しよう
学部ごとに共通テストの配点は異なります。
| 学部名 | 共通テストの配点目安(前期) |
|---|---|
| 医学部医学科 | 約900点中660点(約73%) |
| 工学部 | 約800点中560点(約70%) |
| 人文学部 | 約700点中490点(約70%) |
| 教育学部 | 約700点中455点(約65%) |
🔍 たとえば、人文学部を目指す場合は共通テストで7割以上が必要です。
したがって、夏までに安定してその得点を取れるようになる必要があります。
配点バランスから勉強の優先順位を決めよう
- まずは、共通テスト重視の学部なら、英語・国語・数学の得点力が最優先です。
- 一方で、二次試験の配点が高い学部(例:医学部)では、記述力・論述力の強化が必要です。
- つまり、学部ごとに“得点源”を明確にし、そこに時間をかけましょう。
次に出題傾向を過去問から 読み解こう
- 新潟大学の2次試験では、標準〜やや難レベルの問題が中心です。
- たとえば、英語は長文読解と自由英作文が定番です。
- また、数学では典型問題に加え、論証やグラフの読み取りが問われます。
- このように、過去問で出題形式に慣れておくことが合格への近道です。
最後に模試の活用法を知っておこう
- まずは、模試を「本番形式の練習」として使う意識が大切です。
- 次に、自己採点後は必ず復習し、苦手の洗い出しを行いましょう。
- そして、「どの教科が足を引っ張っているのか」を数値で確認します。
- つまり、模試は“自分の現在地を知るツール”として最大限活用するべきです。
🌸春|基礎固めの スタートダッシュ
【英語】
- まずは、英単語帳1冊(例:ターゲット1900)を毎日50語ずつ暗記する習慣をつける。
- 次に、英文法書(Next Stageなど)を1日1〜2章ずつ進めて基礎文法を整理。
- 加えて、英文解釈の入門書を使ってSVOC構造を理解するトレーニングを始める。
【数学】
- まずは、教科書レベルの例題と基礎問題を繰り返し解いて、計算力を定着させる。
- さらに、『基礎問題精講』などで典型問題のパターンを学ぶ。
- しかしながら、理解に時間がかかる分野はYouTube講義などで補完するのも有効。
【国語】
- 現代文は、まずは読解の基礎(接続語・段落構成)を確認。
- 古文は、文法(助動詞・助詞)と単語帳(ゴロゴ)を毎日10語ずつ覚える。
- 加えて、漢文は句形を少しずつ暗記し、簡単な読解に取り組む。
☀️ 夏|応用力と演習量の底上げ
【英語】
- 次に、長文読解を本格化。週に3〜4題は時間を計って読解する。
- また、文構造を意識して精読しながら、訳せる力を養う。
- さらに、共通テスト対策としてリスニング教材を週2回は取り入れる。
【数学】
- 『1対1対応の演習』などを使い、応用レベルの問題に取り組み始める。
- つまり、基本パターン+論理的思考の組み合わせを身につける時期。
- 加えて、夏の模試に向けて分野ごとの確認テストを実施する。
【国語】
- 現代文は、評論文の論理展開を読み取る練習に力を入れる。
- 次に、古文・漢文は毎日1題ずつ問題演習を行い、実戦感覚を養う。
- つまり、文法+単語の「知識」と読解力の「応用」をつなげることがカギ。
🍂 秋|実戦力の強化と出題傾向への対応
【英語】
- まずは、共通テスト・新潟大学の過去問を分析し、頻出テーマを把握。
- 加えて、英作文や自由記述対策を週1回は取り入れ、記述力を鍛える。
- そして、解いた問題の振り返り(なぜ間違えたか)をノートにまとめる。
【数学】
- ここでは、時間制限を設けて2次試験形式の問題を解くトレーニングを始める。
- さらに、模試の復習を徹底し、自分の苦手分野を言語化・可視化する。
- しかしながら、焦って新しい問題集に手を出すより、今までの反復が重要。
【国語】
- 現代文は、評論と小説の両方を交互に演習し、設問パターンに慣れる。
- また、古文・漢文は過去問を用いて「時間配分」と「得点力」を意識。
- 次に、記述式の練習にも着手し、添削を受ける機会を作る。
❄️ 冬|本番力の完成
【英語】
- まずは、共通テスト予想問題・過去問を時間を計って解く。
- 次に、リスニング対策を仕上げにかかる(過去問+予想問題の音源を活用)。
- さらに、苦手な分野は“単元別”に集中的に演習する。
【数学】
- ここでは、2次試験の過去問を数年分まとめて演習する。
- また、問題ごとに「方針→計算→見直し」の流れを意識。
- つまり、実戦力と試験慣れを同時に鍛えるラストスパート期間。
【国語】
- 共通テスト形式の問題を時間配分に注意しながら週1〜2回は解く。
- そして、設問の傾向と自分の得意不得意を再確認する。
- 加えて、記述対策(必要な学部のみ)は仕上げ段階に入る。
新潟大学に合格する: よくある勉強の悩み
❓ Q1. 新潟大学を目指すなら、まず何をすべき?
▶️ A1. まずは、志望学部の入試方式と配点を把握しましょう。
なぜなら、新潟大学では学部ごとに共通テストと2次試験の比重が異なるからです。
たとえば、医学部や工学部では2次試験の配点が高く、数学・理科対策が特に重要です。
一方で、人文学部や教育学部では共通テストが高配点なので、早い段階から対策を始める必要があります。
つまり、自分の志望学部の特徴を知らないと、効率的な勉強法が立てられません。
❓ Q2. 共通テスト対策はいつから始めればいい?
▶️ A2. 春から始めておくのが理想です。
まずは、英語・数学・国語の基礎固めを徹底しましょう。
次に、夏には応用問題や時間配分の練習に進みます。
そして、秋から冬は共通テスト形式の問題で実戦演習を重ねます。
このように、季節ごとに目的を変えることで、共通テストの得点力が安定します。
❓ Q3. 新潟大学の2次試験で問われる力とは?
▶️ A3. 記述力・論理的思考力・情報整理力が問われます。
たとえば、英語では自由英作文や和訳が出題されるため、構文理解と表現力の両方が必要です。
数学では、途中式をしっかり書く記述型の解答が求められます。
したがって、日頃から「考え方を言語化する練習」を取り入れることが重要です。
❓ Q4. 模試の判定が悪くて不安…どうすれば?
▶️ A4. 模試は「現状を知るための道具」と割り切りましょう。
まずは、なぜ点数が伸びなかったのか原因を分析します。
次に、復習ノートを作って、同じミスを繰り返さないようにします。
そして、間違えた問題を類題で補強することで、苦手を克服していきましょう。
しかしながら、判定だけに一喜一憂せず、「改善できる要素」を探す姿勢が合格への鍵です。
❓ Q5. どんな人が新潟大学に合格しているの?
▶️ A5. 計画的に勉強を継続できる人です。
つまり、「できる人」ではなく「続けた人」が受かる大学です。
毎日少しでも机に向かい、ミスを改善しながら前に進むタイプの人が合格をつかんでいます。
加えて、過去問の傾向を早めに掴み、自分の力を「入試本番用」に調整できた人が有利です。
新潟大学在学生の声|リアルな体験談で モチベーションUP!
🌿 A.Sさん(人文学部・1年)
「私は英語が本当に苦手で、最初は共通テストも5割届きませんでした。
でも、“1日30分だけでも毎日英語に触れる”と決めて、継続。
秋頃には長文がスラスラ読めるようになり、自信に変わりました。
“苦手でもコツコツ続ければ武器になる”と気づけたのが転機でした。
今は、新潟大学で文学や言語を深く学べて楽しい毎日を送っています!」
🧪 K.Nさん(理学部・2年)
「現役時代は全落ち。浪人中も模試はD判定ばかり。
それでも、過去問を1日1題、丁寧に解いて復習ノートを作りました。
“答えよりも過程を大事にする”ことを意識したら、成績が急上昇!
2次試験の数学では自己ベストが出て、逆転合格できました。
大切なのは“焦らず、自分のペースで積み上げること”。
合格してからの学びが本当に楽しいです!」
🍎 M.Hさん(教育学部・3年)
「部活引退が高3の10月で、スタートが周囲より遅かったです。
“もう間に合わないかも…”と思いましたが、1日15時間勉強に切り替えました。
まずは共通テストの得点源を絞って集中対策し、何とか7割突破。
“あと一歩”が届くように2次の国語と英語を徹底強化し、逆転合格!
今では、教職課程で学びながら、小学校教育の現場に出る準備をしています。」
🔬 R.Yさん(工学部・1年)
「共通テストで思ったより点が取れず、後期出願に切り替えました。
不安だったけど、2次試験の数学と物理に絞って対策。
“自分が勝てる科目に集中する”と割り切ったことが功を奏しました。
結果的に、新潟大学工学部に後期合格できたのは、自分の強みに気づけたから。
“選択と集中”が、最後の勝負を決めました。」
新潟大学勉強法: まとめ
まずは、「新潟大学勉強法」における正しい情報と学部ごとの傾向を理解することが、合格への第一歩です。
次に、春から冬にかけて、季節ごとにやるべき内容を明確にし、段階的に学習を進めることが重要になります。
しかしながら、ただ計画を立てるだけでは結果は出ません。
日々の積み重ねと、模試や過去問による振り返りが、確かな成績向上を生み出します。
そして、モチベーションを維持しながら、志望学部に合わせた戦略を実行していくことが、合格を引き寄せる決定打になります。
つまり、「正しい戦略」と「継続力」の両輪が、新潟大学合格というゴールを実現する鍵です。
この記事を参考に、今すぐあなた自身の1年間の勉強計画を立ててみましょう。
東北地方国公立大学の勉強法はこちら!
- 弘前大学編:弘前大学勉強法:最短合格を目指す1年間
- 岩手大学編:岩手大学勉強法:1年間の勉強計画と成功のコツ
- 宮城教育大学編:宮城教育大学勉強法とは?今すぐ始めたい受験対策
- 秋田大学編:秋田大学勉強法:効率重視で逆転合格!
- 山形大学編:山形大学勉強法|1年間で逆転合格!
- 福島大学編:福島大学勉強法:1年間で逆転合格を目指す人へ
関東地方国公立大学の勉強法はこちら!
- 茨城大学編:茨城大学勉強法とは?今始めるべき戦略を解説!
- 筑波技術大学編:筑波技術大学勉強法|戦略的な学習計画とは?
- 宇都宮大学編:宇都宮大学勉強法とは?今すぐ始めたい受験戦略
- 群馬大学編:【群馬大学 勉強法】逆転合格を目指す1年間
- 埼玉大学編:埼玉大学勉強法とは?今から始めて合格をつかむ!
- 東京学芸大学編:東京学芸大学勉強法|合格する1年間の学習戦略
- 東京農工大学編:【東京農工大学勉強法】今すぐ始めたい受験対策
- お茶の水女子大学編:お茶の水女子大学勉強法:徹底解説!
- 東京海洋大学編:東京海洋大学勉強法1年間で逆転合格
- 電気通信大学編:電気通信大学勉強法:戦略的な学習計画
- 政策研究大学院大学編:【徹底解説】政策研究大学院大学勉強法とは?
- 総合研究大学院大学編:総合研究大学院大学勉強法:1年間の戦略的学習法とは?