東京藝術大学国語の対策って、どうすればいいの?そんな疑問を持っている方は、意外と多いのではないでしょうか。まずは知っておきたいのが、東京藝術大学国語は、他大学とはまったく異なる傾向を持つという点です。一般的なマーク式試験とは異なり、表現力・構成力・感性までが問われる記述型問題が中心となっています。しかし、「特別な才能がないと無理」と思う必要はありません。
実は、出題の特徴を理解し、段階的に力をつけることで誰でも十分に合格点を狙えます。
この記事では、
👉 東京藝術大学 国語の出題傾向と構成
👉 評論文・随筆文への対応法
👉 実践的な記述対策とおすすめ参考書
など、合格に必要なすべてをわかりやすく解説します。
とはいえ、対策が遅れると、点差がつきやすいのも事実。だからこそ、早めの準備と正しい勉強法が、東京藝術大学合格のカギを握ります。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
ホームページ:東京藝術大学
出題範囲・形式
- 大学入学共通テストの「国語」が入試で必須科目として課される(多くの学部で国語必須)。
- 国語は現代文を中心とした読解が基本で、評論・説明文・小説等が含まれる形式で、基礎〜標準レベルの読解力が求められます(他の一般入試と同様)。※大学公式の出題傾向は募集要項等で確認できますが、基本は共通テスト形式です。
出題傾向(特徴)
- 読解重視の試験設計:共通テストの国語は、文章全体の主旨・論理・設問に対する正確な読み取りが得点の鍵です。※東京藝術大学独自の二次「国語」試験は基本的にありません(美術・音楽等は共通テスト利用)。
- 記述は共通テストに含まれない:記述式問題は導入が見送られているため、基本は選択式+多肢選択+読解中心です。
- 漢字・語彙・現代文読解力が重要:共通テスト国語では語彙・漢字の正確さに加え、長文を読み切る力が問われます。※過去問等を通じて想定演習が有効です。
対策のポイント
- 共通テスト形式の演習を重視し、現代文の長文読解力を高める。
- 語彙・漢字・文法の基礎を固め、設問形式に慣れる。
- 東京藝術大学は国語独自問題より共通テスト国語の得点重視の入試設計であるため、共通テスト対策=国語対策になります。
(※東京藝術大学は美術・音楽など専門領域の実技・二次試験が主で、国語は共通テスト科目としての扱いが中心です。)
おすすめ参考書まとめ
📘 現代文 — 『入試現代文へのアクセス』
現代文は「なんとなく読む」だけでなく論理的に読む力が必要なため、基礎〜応用まで段階的に身につけられるこの1冊は特に有効です。問題演習+解説で、本文の構造把握や論理展開の読み方を効率的に練習できます。
📗 古文 — 『読んで見て覚える重要古文単語315』
古文対策では、単語・文法・背景知識が鍵ですが、頻出語を体系的に覚えられるこの単語帳は必須レベルです。単語力がつくと、読解スピードや内容理解が格段に上がります。
📕 漢文 — 『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』
漢文はパターン(句法・語彙)が比較的決まっているため、効率よく覚えられるゴロ合わせやコツの解説があるこの本は、句法習得と読解力アップに役立ちます。共通テストから私大・二次まで幅広く対応できます。
✍️ 勉強のポイント
- まずは現代文で文章の読み方の基礎を固め、次に古文で古語知識の定着をはかり、そして漢文で句法のパターン理解を進める、という順序で取り組むと効果的です。
よくある質問まとめ
1. 東京藝術大学の国語はどのように出題されますか、そしてどのように対策すべきですか?
答え: 東京藝術大学(例:美術学部・工芸科・音楽学部など)の多くは大学入学共通テストの「国語」を入試科目として利用するので、共通テストと同じ形式の現代文・古典(現代語文含む)読解力をしっかり身につける必要があります。
2. なぜ記述式ではなく選択式中心なのですか、だからこそどんな勉強が重要ですか?
答え: 共通テストの国語は記述式が導入見送りとなっているため、文章全体の構造や主旨を正確に読み取る力が問われる選択式中心の出題です。そのため、論理的な読解力と設問での細かい条件把握が得点の鍵になります。
3. しかし古典は必要なのですか、そしてどのように対策すればいいですか?
答え: 共通テストの国語では「近代以降の文章」と古典(古文・漢文)も含まれるため、古典の基本文法・語彙・読み下しも学習しておく必要があります。
4. 良い読解対策はどう進めればいいですか、そのために何を意識すべきですか?
答え: 共通テストでは長文の読解量が多いので、設問ごとに本文のどの部分を根拠にするかを意識しながら読む練習を積むことが重要です。その結果、主張・理由・具体例のつながりを正確に把握できるようになります。
5. 時間配分で気をつけるべきことは何ですか、さらにどんな練習が効果的ですか?
答え: 共通テスト形式では時間内に長文を読み、設問に答えるスピードが求められるため、過去問演習で時間を区切って読む練習を重ね、設問形式=本文マーク→該当箇所で根拠を確認する、という型を身につけることが効果的です。
今日の語彙問題
次の文中の下線部の意味として最も適切なものを選びなさい。
彼の論説は非常に鋭敏で、芸術の本質を的確に捉えている。
- 鋭く鈍感なこと
- 感覚や理解力が鋭いこと
- 物理的に尖っていること
- あいまいで不明確なこと
【解答】
2. 感覚や理解力が鋭いこと
【解説】
「鋭敏」とは、「感覚や理解力が非常に鋭く、敏感であること」を意味します。
この文では、「芸術の本質を的確に捉えている」という文脈からも、感覚や思考の鋭さを表す言葉だとわかります。
一方、選択肢1の「鋭く鈍感」は矛盾した表現で意味が通りません。
選択肢3の「物理的に尖っていること」は、「鋭い」の別の意味ですが、ここでは不適切です。
また、4の「あいまいで不明確なこと」は「鋭敏」とは反対の意味です。
このように、芸術や評論で使われる語彙は文脈を読む力が問われるため、語彙問題は文脈理解の訓練にもなります。
まとめ:東京藝術大学 国語対策は「表現力」と「感性」
東京藝術大学の国語(大学入学共通テスト)対策では、まず共通テスト形式の現代文・古典読解に慣れることが重要です。なぜなら、国語は文章の主旨・論理・文脈把握が得点の鍵となり、選択式中心の設問でも正確な読み取り力が必要だからです。そして、古典もまれに出題されるため基礎文法と語彙を押さえつつ、現代文の長文読解演習を重ねることで読解力と解答スピードを同時に強化できます。また、過去問を繰り返し解くことで出題パターンや設問形式の傾向に慣れ、解答の根拠を本文から素早く見つけ出す力が伸びます。したがって、日々の学習では現代文の論理的な読解と古典の基礎的な知識をバランスよく学習し、時間配分を意識した実戦演習で実力を固めることが合格への近道です。
東京藝術大学全体の勉強法はこちら!
東京藝術大学編:【東京藝術大学勉強法】今すぐ始めたい学習戦略
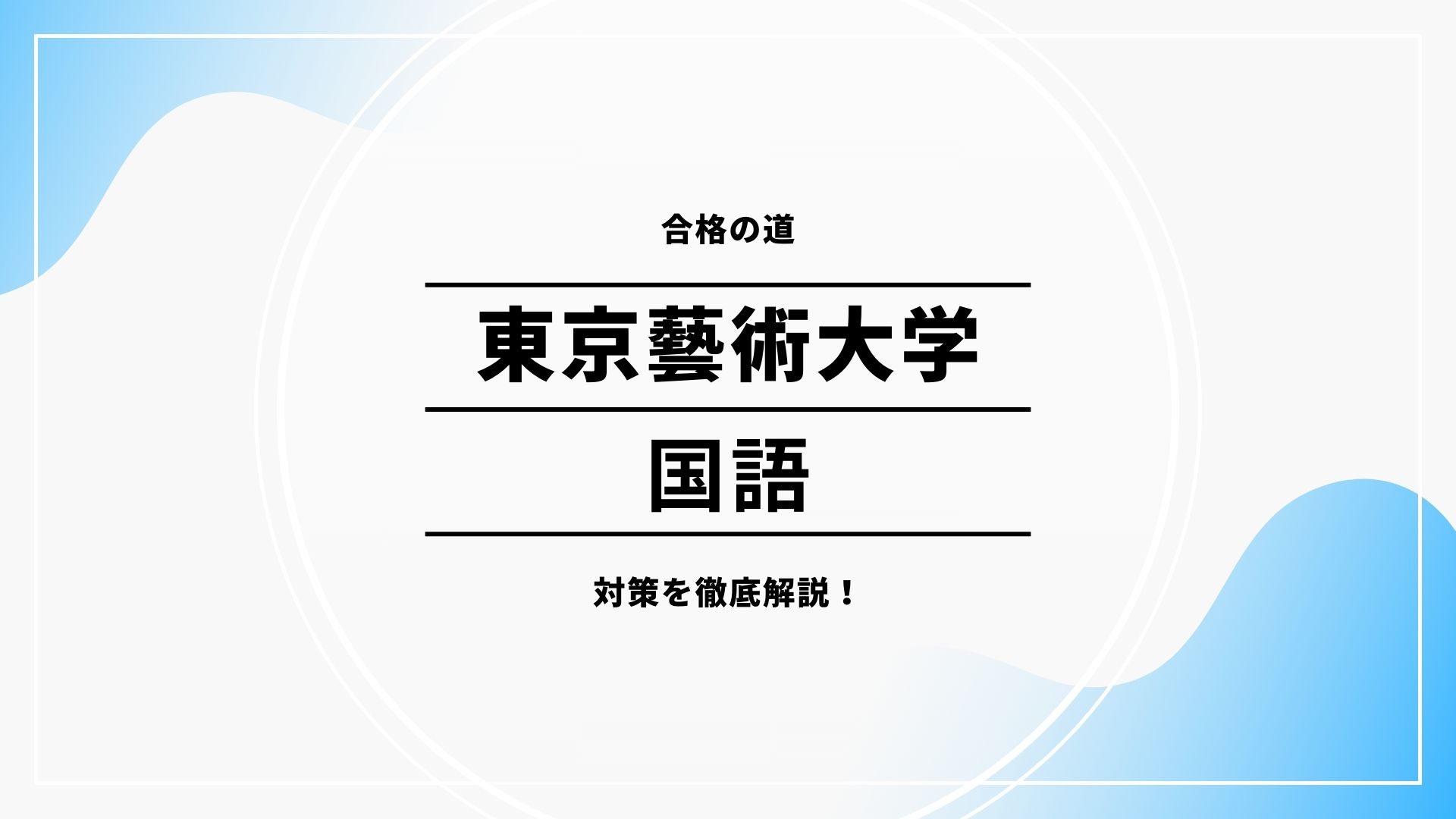
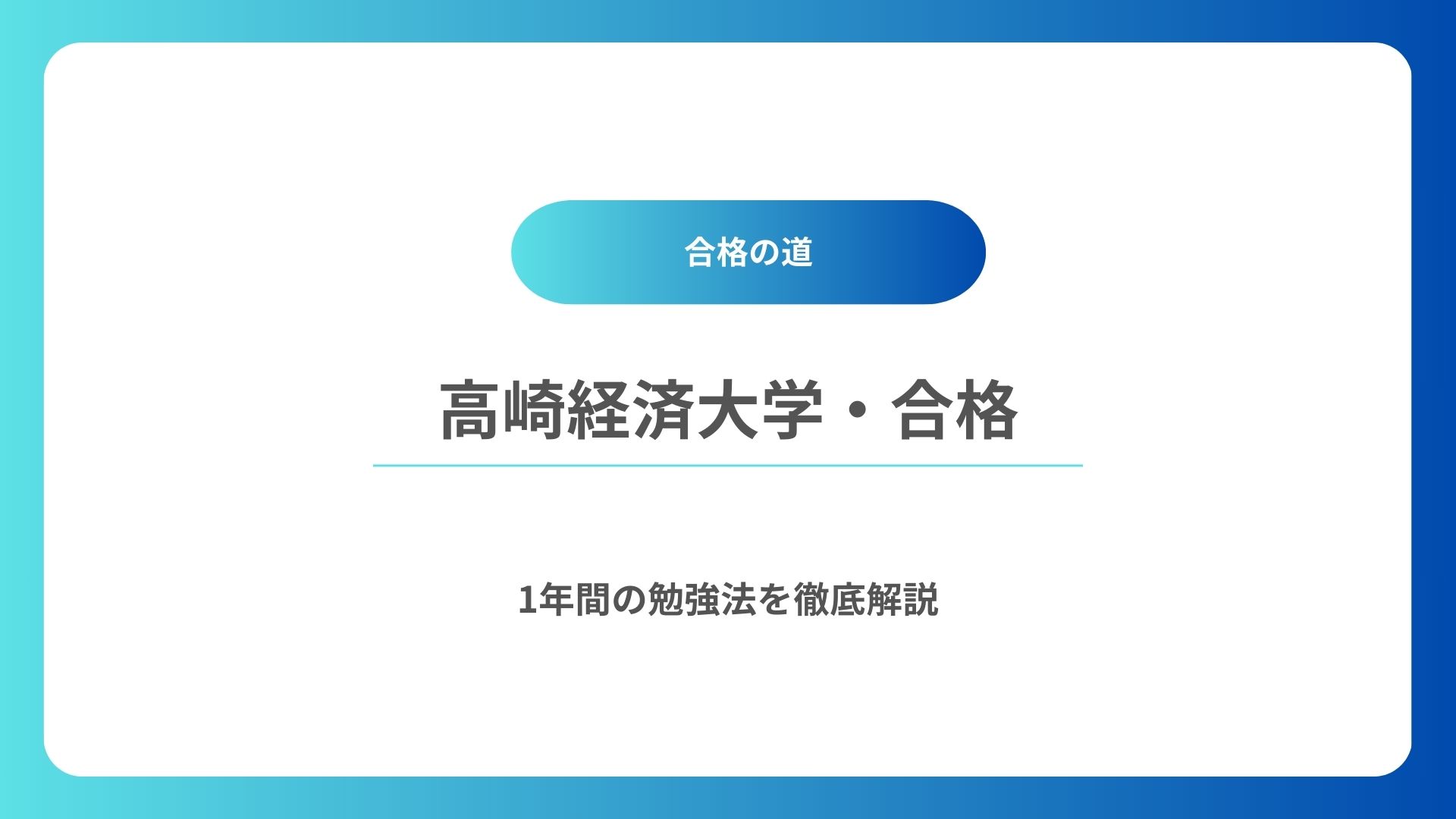
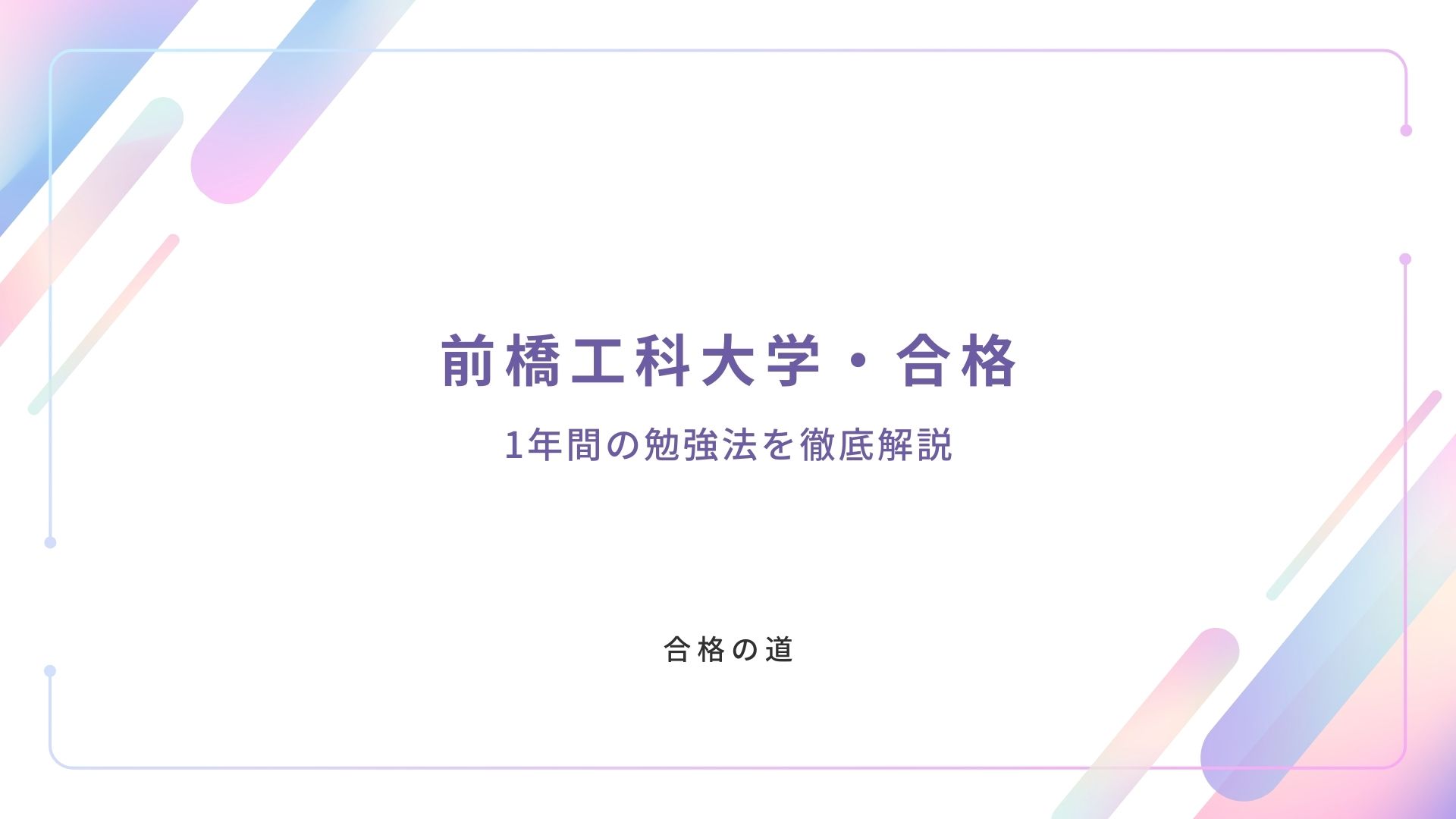
コメント