目次
埼玉大学勉強法を知りたいけど、何から始めればいいの?
そんな悩みを抱える受験生は少なくありません。特に浪人生や高2・高3の受験生にとって、効果的な埼玉大学勉強法を1年間かけて実践することは、合格への最短ルートとなります。
この記事では、実際に多くの合格者が実践してきた埼玉大学合格に特化した勉強法を、月ごとのスケジュールとともに詳しく解説します。偏差値が今どの位置でも大丈夫。1年あれば、合格圏に到達することは十分可能です。
他の受験生と差をつけたい方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
今こそ、あなたの勉強を“合格仕様”に変えるときです。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
最新の入試情報はここから!:埼玉大学
🌸 春(4月〜6月)|基礎を固め、土台を築く時期
英語
- まずは中学〜高1レベルの英文法を総復習(Next StageやVintageなどを活用)
- さらに、単語帳(ターゲット1900やシス単)で語彙力を強化
- 加えて、英文解釈(入門英文解釈の技術70など)を少しずつ開始
数学
- ここでは、青チャートやFocus GoldなどでⅠA・ⅡBの基礎を徹底
- また、例題・重要問題を解きながら公式の使い方に慣れる
- そのうえで、ミスの原因をノートに書き出して復習習慣を作る
国語
- 現代文:まずは読解の基礎(キーワード読解など)を理解
- 古文:文法と単語を毎日コツコツ(古文上達やゴロゴ)
- なお、漢文は後回しでもOKだが、句法だけは春のうちに触れておくと安心
理科(物理・化学・生物)
- まず教科書レベルを丁寧に読む
- そのうえで、基礎問題精講やセミナー系で簡単な演習を開始
- 理解重視。焦らず確実に
社会(日本史・世界史・地理・公民)
- まずは全体像をつかむ。実況中継やマーチ向け参考書が役立つ
- さらに、用語集や一問一答を週1で進めておくと後が楽になる
☀️ 夏(7月〜8月)|演習とアウトプット中心で実力を伸ばす
英語
- ここで長文読解演習を本格化(やっておきたい500〜700)
- また、文法・語法は引き続き反復で記憶定着
- 加えて、共通テスト形式の問題集にも挑戦
数学
- ⅠA・ⅡBの標準問題レベル(共通テストレベル)を反復
- 余裕があればⅢの基本概念に入る(理系のみ)
- さらに過去問を軽く触れることで出題形式に慣れる
国語
- 長文読解演習(センター過去問や共テ形式)を中心に
- 古文は読解演習と並行して文法の総仕上げ
- 漢文は句形と読解問題に取り組む(漢文ヤマのヤマなど)
理科
- 各分野ごとに基礎問題を一通り演習(物理なら力学、化学なら化学基礎)
- 模試を利用して「自分の弱点」を可視化
- さらに、時間を意識して解く練習を始める
社会
- 通史の演習+文化史・時代背景の暗記を同時並行
- 一問一答で抜け落ちをチェック
- なお、地理や倫理系は資料集を活用した学習が効果的
🍂 秋(9月〜11月)|志望校レベルに照準を合わせて仕上げに入る
英語
- 志望学部の過去問を分析し、形式別演習(和訳・英作・要約など)
- 英作文対策も本格化(英作文ハイパートレーニングなど)
- なお、速読練習と音読は継続
数学
- 過去問演習+模試対策で実戦力を強化
- 苦手単元を洗い出し、ピンポイントで演習
- 記述力を意識した解答練習を始める
国語
- 共通テスト形式の現代文演習と、マーク模試の過去問で実戦練習
- 古文・漢文は精読よりスピード重視へシフト
- さらに、読解問題で点数が安定するよう工夫
理科
- 出題傾向に合わせて演習(過去問や類題集を活用)
- 加えて、ミスの傾向を分析し、復習重視で得点力を伸ばす
- 特に理科は「時間配分」と「計算力」が差になる
社会
- 論述がある学部は、記述問題対策を強化
- 一方、共通テスト型のみの場合はマーク練習を重視
- 重要年代や語句の整理は秋までに完成させておく
❄️ 冬(12月〜2月)|総仕上げ&志望校対策の徹底強化
英語
- 志望学部の過去問を本格的に解き込み
- ミスの原因を分析し、パターン化された対応策を持つ
- 音読とリスニング対策も忘れずに継続
数学
- 実戦演習+記述問題演習で最終調整
- 解法の引き出しを増やし、「捨て問・得点問」の見極め力を養う
- 本番を意識したタイムトライアルも有効
国語
- 共通テスト直前は現代文と古典の時間配分訓練
- 難問よりも「確実に得点できる問題」に集中
- 漢字・文法・文学史など短期間で上げやすい分野を最終調整
理科
- 志望学部の配点を考慮して「得意分野」で点を稼ぐ戦略に切り替える
- 化学や物理では暗記分野(無機・有機など)の再確認も忘れずに
社会
- 最後の仕上げとして、模試や過去問を通じて点数の安定化を目指す
- 一問一答・資料集の見直しで“取りこぼしゼロ”を目指す
埼玉大学 合格を遠ざけるNG勉強法
NG勉強法①:共通テストを“通過点”として甘く見る
→ 配点が高く、ここで差がつく!
埼玉大学では共通テストの配点比率が高く、特に教養学部・経済学部などでは7~8割を占めることもあります。
「共テは最低限でOK」と考えるのは非常に危険です。
改善策:
- 夏からマーク演習を開始し、形式に慣れる
- 科目別に「正答率が低い単元」を分析し、集中的に潰す
- 模試は判定だけでなく時間配分・設問分析に活用する
NG勉強法②:2次試験の記述対策を後回しにする
→ 記述力=合否を分ける本質的評価ポイント
特に理学部・工学部・教育学部では2次試験での記述式の得点が大きな意味を持ちます。
「書けばどうにかなる」は通用しません。
改善策:
- 数学や理科の記述は「考え方」を丁寧に書く練習を重視
- 英語の和訳・英作文は週ごとにテーマを絞って添削→改善
- 2次試験の過去問は最低3年分を複数回演習する
NG勉強法③:得意・苦手の偏りが激しいまま本番を迎える
→ 総合力重視の国立大では、苦手放置が致命的!
文理問わず、1科目の失敗が足を引っ張る可能性が高いのが埼玉大学。
「この教科が得意だから大丈夫」は成り立ちません。
改善策:
- 毎週の勉強計画に「苦手科目の時間」を必ず確保
- 模試後に「苦手の原因」を分析 → 対策の優先順位を明確に
- 苦手科目は基礎+反復重視で“底上げ”を狙う
NG勉強法④:英語は長文だけ、または文法だけの片寄り学習
→ 埼玉大英語は“全領域型”。偏りは失点リスク!
埼玉大学の英語は、長文読解に加えて文法問題・英作文・和訳などもバランスよく出題されるため、1分野に偏った対策では高得点は望めません。
改善策:
- 長文読解の中で「文構造(SVOC)」を意識した精読訓練
- 英作文は「書く→添削→書き直す」の3ステップで強化
- 和訳問題は、自然な日本語になるまで練習を繰り返す
NG勉強法⑤:過去問を1回解いて終わりにする
→ 傾向把握・弱点補強に活用しないと意味がない!
過去問を「解いた実績」にしてしまい、復習や分析を怠るのは典型的なNG勉強法です。
出題傾向の変化や頻出テーマを把握できないまま受験することになります。
改善策:
- 過去問は1年分×3回以上の演習+解き直し
- ミスの原因を記録し、類題や基本事項で補強
- 学部別に「出題の傾向・形式」を事前に一覧化して整理
❓埼玉大学勉強法に関するよくある質問【Q&A形式】
受験生や保護者の方からよく寄せられる質問に対し、実践的かつ戦略的な観点から回答していきます。
小見出しごとに質問を整理し、情報の取り出しやすさにも配慮しています。
❓ Q1. 埼玉大学の受験に向けて、いつから本格的に勉強を始めればいいですか?
▶️ A.
まずは高2の終わり〜高3の春には本格スタートを切るのが理想です。
その一方で、浪人生や再チャレンジ組なら「今すぐ始めること」が大前提になります。
加えて、早期にスタートすることで、夏以降に過去問演習や応用問題に時間を割く余裕が生まれます。
❓ Q2. 埼玉大学に合格するには、共通テストと二次試験のどちらが重要ですか?
▶️ A.
これは志望学部によって異なります。
たとえば教育学部や工学部の一部では二次試験の配点が高くなる傾向があります。
その一方で、経済経営学部や教養学部では共通テスト重視型の学部も存在します。
したがって、「まずは配点比率を確認し、自分の得意・不得意を加味した戦略」が必要です。
❓ Q3. 英語が苦手です。どのように勉強すれば埼玉大学レベルまで届きますか?
▶️ A.
英語に関しては、語彙・文法・構文の基礎を徹底的に固めることが最優先です。
とはいえ、長文が頻出な学部も多いため、徐々に読解トレーニングへ移行する必要もあります。
また、過去問を分析すると「文法ミス・英作文・和訳」で点を落とす受験生が多いので、アウトプット型の練習も欠かせません。
❓ Q4. 模試の判定がずっとD判定以下ですが、逆転合格は可能ですか?
▶️ A.
結論から言うと、逆転合格は可能です。
その理由は、模試の判定はあくまで「現時点での得点力」を表しているにすぎないからです。
加えて、秋以降に得点が伸びやすいのは「復習・分析」を徹底できた受験生です。
とはいえ、何も考えずに量だけ増やしても効果は薄いため、自分の弱点を特定し、そこに集中する戦略が必要です。
❓ Q5. 科目数が多く、何から手をつければいいかわかりません…
▶️ A.
このようなときは、配点が高い or 得点源にできる科目から優先するのが基本です。
たとえば共通テストの配点が高い学部なら、まずは英語・数学・国語から重点的に対策すべきです。
また、得意科目を先に伸ばすことで自信がつき、全体の学習効率も上がります。
一方で、苦手科目の放置は後半に大きく響くので、夏までには着手することを強くおすすめします。
❓ Q6. 推薦入試や学校推薦型選抜も狙えますか?
▶️ A.
はい、埼玉大学では一部学部で推薦入試(学校推薦型選抜)が実施されています。
ただし、評定平均や課外活動、小論文、面接の対策が必要になるため、準備には時間がかかります。
加えて、募集人数が少ないため、安全策として一般入試の対策も並行するのが現実的です。
まとめ|埼玉大学勉強法を確立すれば、合格は現実になる
ここまでご紹介してきたように、埼玉大学に合格するためには、季節ごとの学習戦略と科目ごとの勉強法を正しく組み合わせることが不可欠です。
まずは、「基礎固め」→「演習強化」→「過去問対策」→「総仕上げ」という1年の流れを意識することが重要です。
加えて、自分の学部の出題傾向や配点を理解し、効率よく得点源を育てていくことが合格の近道になります。
その一方で、すべてを完璧にこなそうとするあまり、途中でペースを崩してしまう受験生も少なくありません。
とはいえ、継続的に努力し、柔軟に勉強法を調整することができれば、逆転合格も十分に可能です。
つまり、成功のカギは「正しい情報」と「行動力」にあります。
さらに、先輩たちの声にもあったように、モチベーションの維持や目標の明確化も大切な要素です。
受験勉強は長く、時には苦しいものですが、戦略的な埼玉大学 勉強法を確立すれば、その努力は確実に実を結びます。
あなたも今日から、自分だけの合格戦略を立てて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
科目別対策はこちら!
国語編:埼玉大学国語の対策法|バランスよく攻略しよう – 合格の道

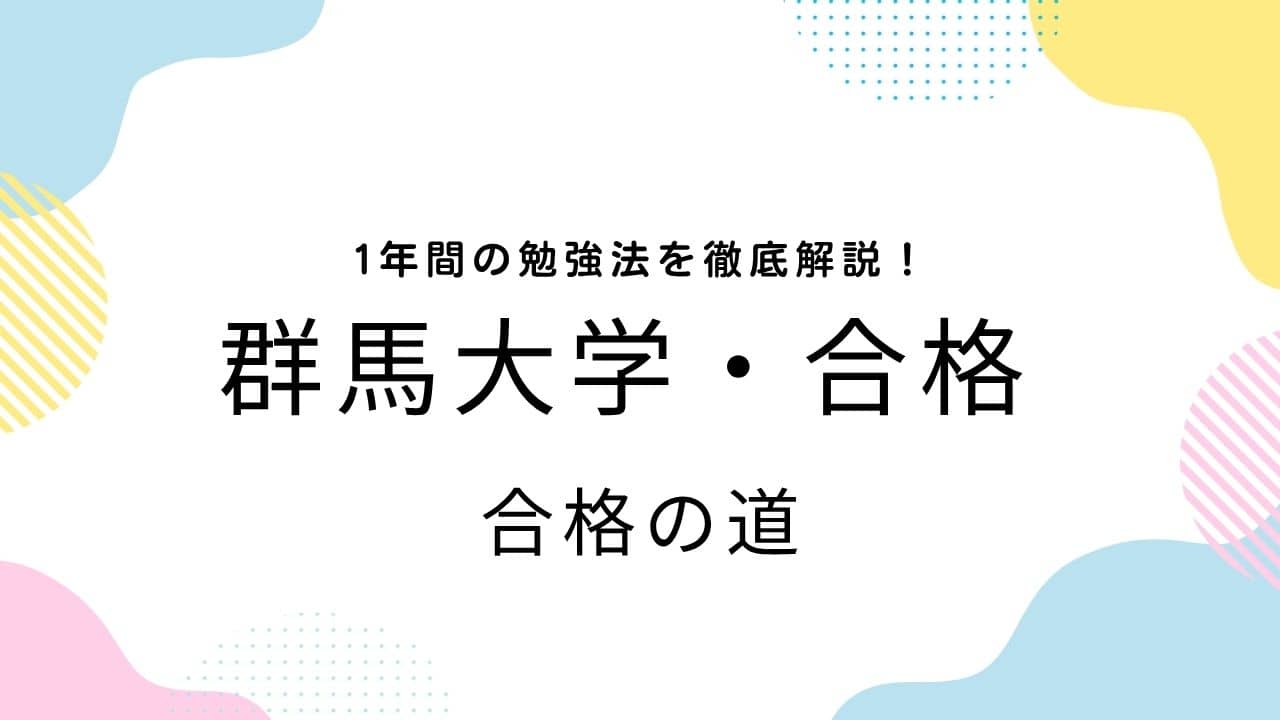

コメント