「電気通信大学勉強法」を知りたいあなたは、きっとこんな疑問を持っているはずです。
- 今から1年で電通大に受かる方法は?
- どんな勉強をすれば合格できるのか?
- 合格者はどんなスケジュールで動いたのか?
結論を先に言えば、1年での合格は十分に可能です。ただし、必要なのは正しい戦略と計画的な勉強法です。
電気通信大学の入試には特徴があります。がむしゃらに勉強しても成果は出にくいのです。出題傾向を押さえた効率的な対策が求められます。
この記事では、1年間の具体的な勉強法を紹介。スケジュールの立て方や教科別の対策も解説します。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
最新の入試情報はここから!:国立大学法人 電気通信大学
電気通信大学勉強法(季節、教科別)
🌸 春|基礎固め期
英語
- まずは、高校基礎英文法(Next Stage、Vintageなど)を総復習
- 次に、英単語帳(ターゲット1900など)を1日30〜50語ずつ暗記
- 加えて、共通テストレベルの長文読解を週2〜3本読む(速読意識)
数学
- まずは、教科書レベル〜青チャートの例題を1周
- 特に、苦手な分野(図形・整数など)は重点的に復習
- その後、学校配布の問題集や標準問題精講を取り入れる
物理・化学
- まずは、教科書+基礎問題精講などで全分野を一通り学習
- 次に、重要な公式・現象をまとめて暗記(ノート化がおすすめ)
- 加えて、基礎〜標準レベルの問題演習を毎日継続
☀️ 夏|実力強化期
英語
- ここでは、共通テストの過去問(または予想問題)を実施開始
- 加えて、英作文の型を覚える(自由英作文・和文英訳)
- 次に、音読とシャドーイングで英語の処理速度をUP
数学
- 最初に、青チャート・Focus Goldの標準問題を一通り演習
- その後、応用問題(1対1対応の演習など)にステップアップ
- 特に、過去問と似た形式の問題を意識して解くことが重要
物理・化学
- まずは、分野ごとの演習量を増やして解法を定着
- 次に、共通テスト形式の問題に触れて時間配分を練習
- 加えて、公式の使い方を説明できるように復習する
🍁 秋|応用・実戦期
英語
- まずは、二次試験レベルの長文(過去問・東大京大レベル以外)に挑戦
- 次に、英作文は週1で添削・見直しを行う
- 加えて、語彙の見直し(ターゲット→鉄壁などに切り替えるのも◎)
数学
- ここでは、赤本(過去問)を使って形式と傾向に慣れる
- その後、記述式の解答作成に時間をかけて練習
- 特に、完答できなくても部分点を意識した解き方を訓練
物理・化学
- まずは、演習を通じて「パターン認識力」を養う
- 次に、年度別の過去問に取り組み、制限時間内に解く練習を行う
- 加えて、記述式問題への対策も少しずつ始める
❄️ 冬|総仕上げ期
英語
- 最終的に、共通テスト+個別試験の過去問を交互に解く
- 加えて、苦手分野(リスニング・語彙・文法など)を短期集中で克服
- 次に、英作文のテンプレを最終確認し、安定した得点源にする
数学
- まずは、過去問を1日1題ペースで本番形式で解く
- 次に、見直しノートを活用してミスを反復学習
- 加えて、頻出分野(微積、数列、ベクトル)は徹底的に仕上げる
物理・化学
- ここでは、時間を測って過去問を本番同様に解く訓練を中心に
- 加えて、忘れていた知識やパターンを短時間で総復習
- 最終的に、解法を頭から説明できるレベルまで到達するのが理想
直前期|最終確認
- 共通テスト結果を踏まえて志望学科の調整を検討
- 苦手分野を集中的に潰す時間にあてる(全科目共通)
- メンタル・体調管理を最優先にし、無理な追い込みは避ける
電気通信大学 合格を遠ざけるNG勉強法
NG勉強法①:数学の論理的思考を鍛えずに暗記だけで乗り切ろうとする
→ 理解と応用が必須の大学だから、暗記偏重は致命的
電気通信大学では、数学的な論理構築や問題解決力が求められます。
公式や解法の丸暗記だけでは太刀打ちできません。
改善策:
- 問題の背景にある理論や証明を理解することに注力する
- 演習問題では「なぜそうなるのか」を言語化して説明できるようにする
- 基本から応用まで幅広く練習問題をこなす
NG勉強法②:プログラミングや情報系の基礎を軽視する
→ 情報科学の基礎知識が問われるので避けて通れない
情報系学部の基礎はプログラミングやアルゴリズム。試験範囲にも含まれることが多いです。
改善策:
- 簡単なプログラミング演習を早めに始める
- 基本的なデータ構造やアルゴリズムの理解に力を入れる
- 過去問や模試で情報系の問題を繰り返し解く
NG勉強法③:英語は単語や文法の暗記だけに終始する
→ 専門科目も英語文献を扱うため、読解力が必要
技術系の論文や資料は英語で書かれていることが多く、英語の読解力が必須です。
改善策:
- 長文読解を中心に、技術的な内容も含む英文を読む訓練をする
- 英作文や要約練習で表現力も磨く
- 専門用語の英語理解にも注力する
NG勉強法④:過去問をただ解くだけで傾向分析をしない
→ 問題傾向と自分の弱点を把握しないと効率が悪い
過去問は戦略的に使わないと意味がありません。
改善策:
- 出題形式や頻出分野を分析し重点的に対策
- 間違えた問題の原因を詳しく検証し復習計画を立てる
- 3年分以上を繰り返し解く
NG勉強法⑤:理論の理解を避けて公式暗記に逃げる
→ 電通大は理論的理解がないと応用問題で苦戦する
通信や電子回路などの理論的な基礎を深く理解することが求められます。
改善策:
- 講義ノートや参考書で理論を丁寧に読み込む
- 問題を解く際は理論のどこが使われているか意識する
- 分からない部分は早めに質問や調べる習慣をつける
NG勉強法⑥:面接や志望理由の準備を怠る
→ 技術的素養だけでなく志望動機や将来像も重要視される
面接では研究や学びたい分野への熱意を具体的に伝える必要があります。
改善策:
- なぜ電気通信大学で学びたいのか、自分の言葉でまとめる
- 将来やりたいことや興味のある研究テーマを具体化する
- 模擬面接を重ねて質問に自信を持って答えられるようにする
電気通信大学勉強法 よくある質問(Q&A)
Q1. 電気通信大学に合格するには、1日どれくらい勉強すべきですか?
👉 A. 最低でも平日3〜4時間、休日は6時間以上を目安にしましょう。
まずは、部活動や学校の授業と両立しやすい時間配分を作ることが重要です。
次に、夏以降は過去問演習や応用対策が増えるため、学習時間は徐々に増やす必要があります。
最終的には、直前期には平日5時間、休日は8時間以上の勉強が理想的です。
Q2. 電気通信大学に特化した参考書・問題集はありますか?
👉 A. 電通大専用の問題集は少ないため、傾向が近い国公立大の教材を活用しましょう。
たとえば、数学や物理では「名門の森」や「標準問題精講」などが効果的です。
また、「赤本」で実際の出題形式に慣れることも極めて重要です。
加えて、理科の記述対策には「重要問題集」や「化学の新演習」などもおすすめです。
Q3. 共通テストと個別試験、どちらを重視すべきですか?
👉 A. 両方大切ですが、最終的に差がつくのは個別試験です。
まず、共通テストは足切りや総合評価に影響します。
しかし、電気通信大学の前期入試では個別試験(2次試験)の配点が高く、実力が問われます。
そのため、共通テストで安定して得点しつつ、秋以降は二次対策を重点的に行いましょう。
Q4. 浪人生と現役生で戦い方に違いはありますか?
👉 A. はい、それぞれに合った戦略が必要です。
現役生は、まず学校の授業を基盤としながら、早めに復習と問題演習を始めることが鍵です。
一方、浪人生は時間に余裕がある分、基礎の穴を完全に埋めた上で、応用に時間を割けるというメリットがあります。
とはいえ、いずれの場合でも、自分に合ったスケジュールと参考書の選定が最重要です。
Q5. 電通大の物理や数学は難しいって本当ですか?
👉 A. 難易度は高めですが、出題傾向に特徴があるため対策は可能です。
たとえば数学では、誘導に従って論理的に思考を進める形式が多く見られます。
物理も、公式暗記ではなく「現象の理解と数式の応用」が問われる傾向です。
そのため、標準問題をじっくりと理解し、過去問で形式に慣れることが重要です。
Q6. 最後の1ヶ月は何を重視すべきですか?
👉 A. 弱点補強+過去問演習を組み合わせるのが効果的です。
まず、時間を測って実戦演習を繰り返しましょう。
次に、ミスの見直しを徹底し、「得点力」を上げる工夫が必要です。
さらに、過去に出た問題の“型”を整理し、本番で慌てないよう準備することが鍵です。
Q7. モチベーションが続かないときはどうしたらいいですか?
👉 A. 短期目標と成果の見える化がカギです。
たとえば、「英単語300語を3日で覚える」「化学の○○分野を1週間で仕上げる」など、
明確で達成感のある小目標を設定してみましょう。
また、進捗をノートやアプリで可視化すると、モチベーション維持につながります。
Q8. 電通大の過去問はいつから始めるべきですか?
👉 A. 遅くとも秋(9月)からは取り組み始めるのがおすすめです。
まず夏までは基礎〜標準問題で実力を養成。
その後、9月以降に実際の出題傾向や形式を確認しながら過去問演習へ移行します。
なお、過去問は「解く→分析→類題演習」の流れで活用することが効果的です。
電気通信大学勉強法 まとめ
ここまで、「電気通信大学勉強法」について、季節別・教科別・体験談・Q&A形式で具体的に解説してきました。
まず押さえておきたいのは、電気通信大学の入試では基礎力と論理的思考力の両方が求められるということです。
したがって、ただ暗記するだけでなく、「なぜそうなるのか?」を理解する勉強法が合格のカギになります。
また、時期ごとの戦略を明確にすることで、1年という限られた期間でも着実に合格レベルへ到達することは十分可能です。
さらに、過去問分析や教科ごとの傾向把握に加えて、自分に合った教材・学習ペースの見極めが重要です。
特に秋以降は、「本番で得点する力」を意識したアウトプット重視の勉強に切り替えていきましょう。
最後に、受験勉強で最も大切なのは「継続すること」です。調子の良い日もあれば、つまずく日もあります。しかし、小さな積み重ねがやがて大きな自信と結果につながります。
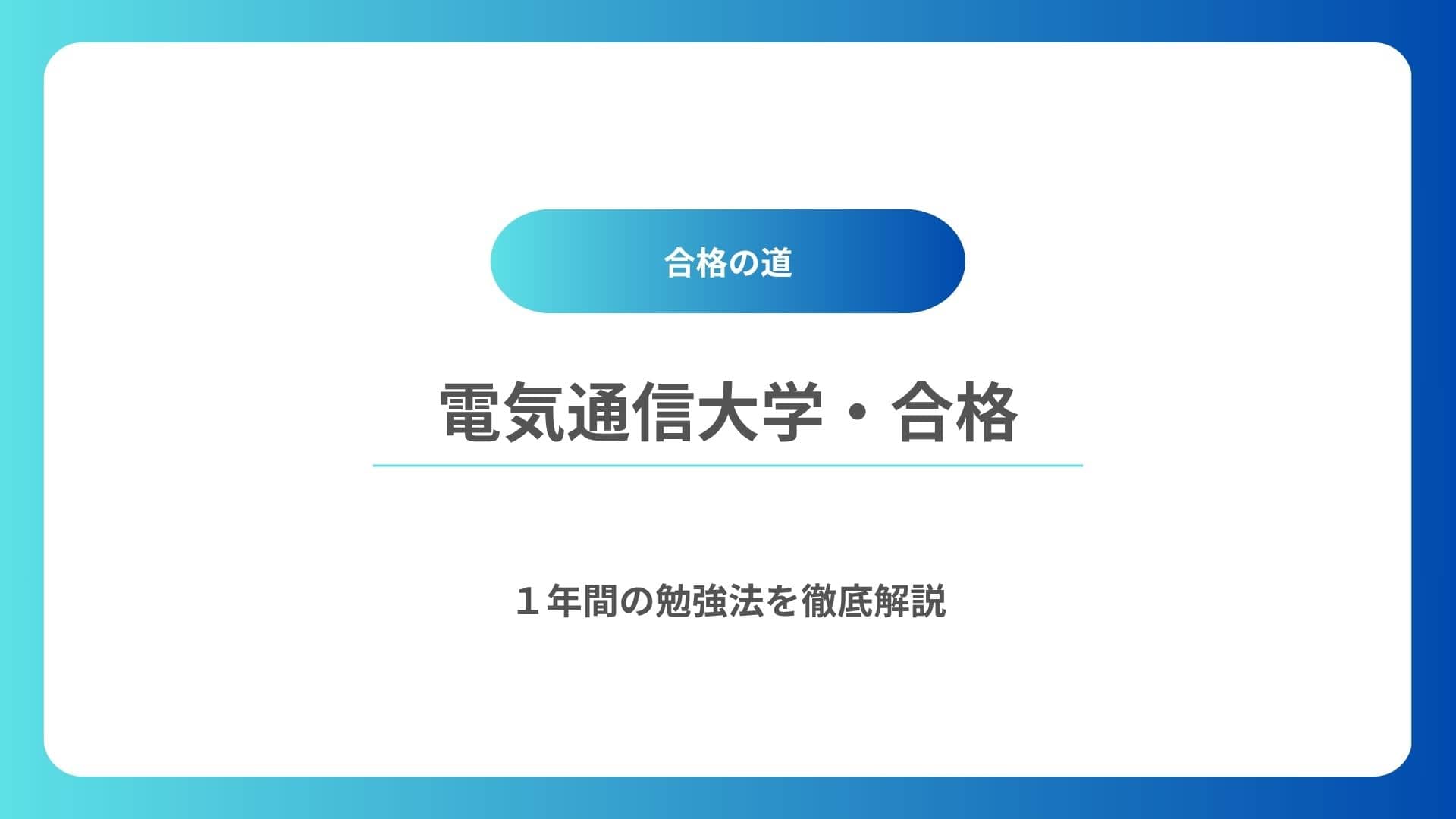
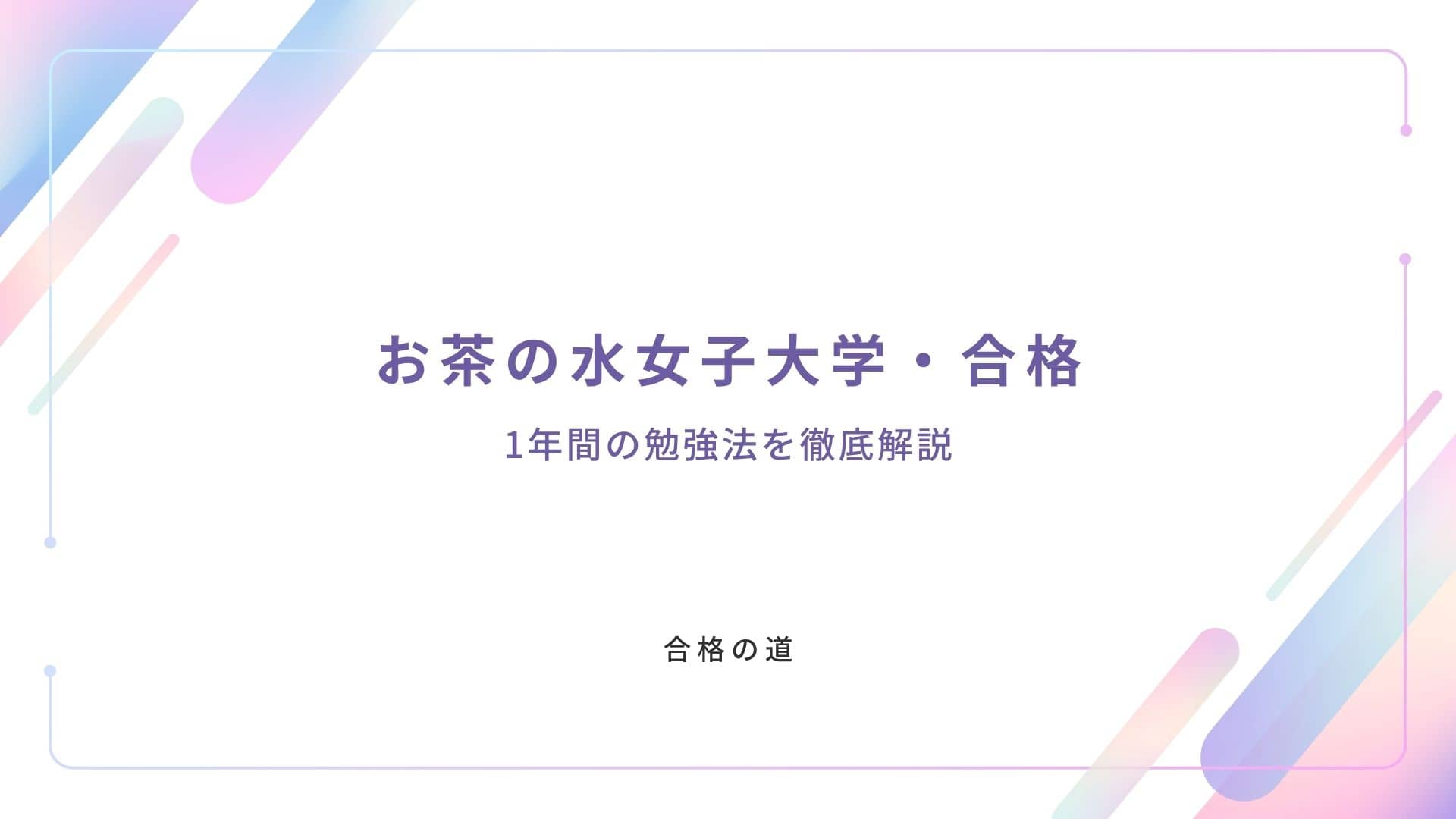
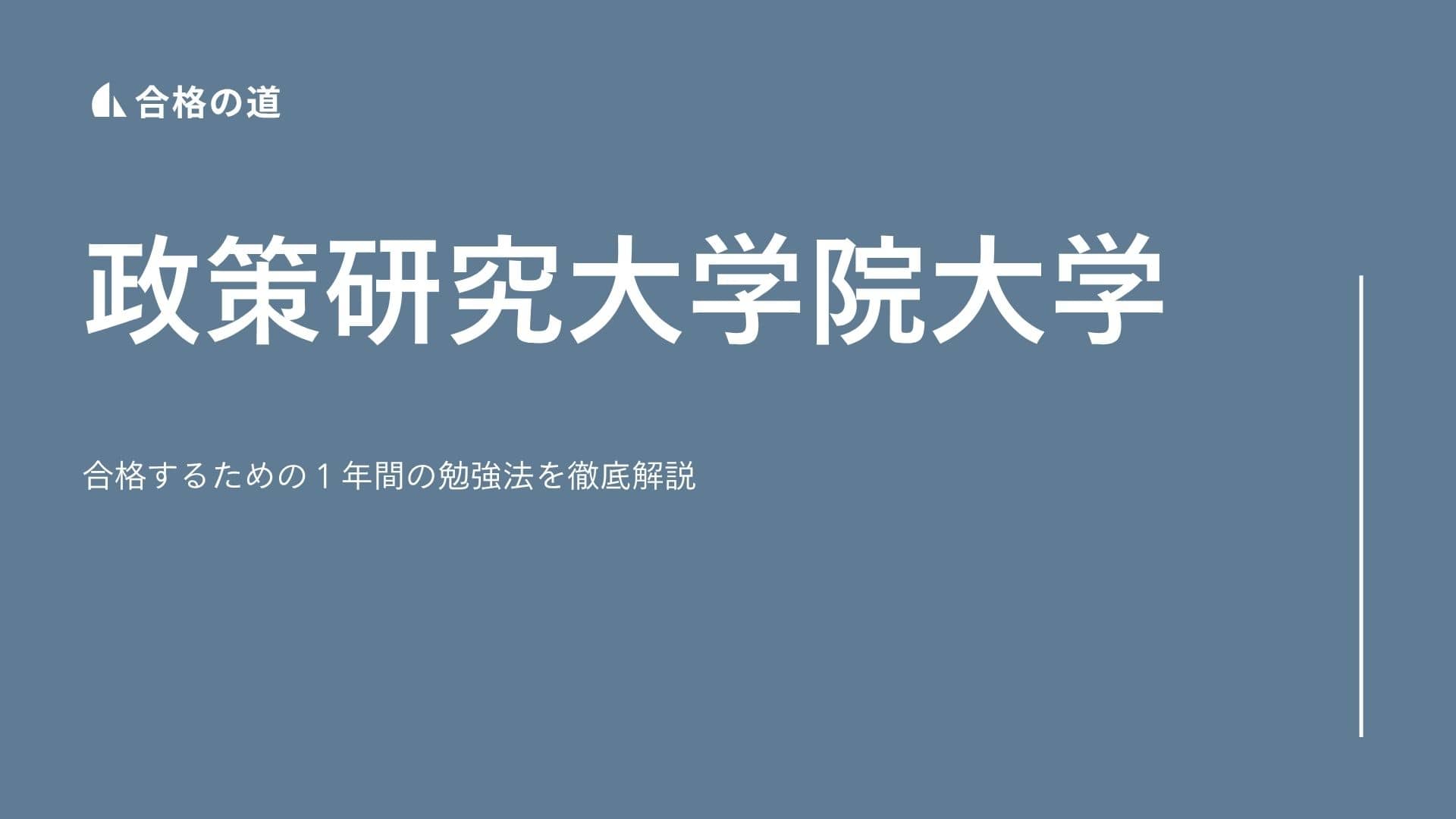
コメント