目次
大学受験の中でも、合否を分ける重要科目のひとつである数学。この記事では、小樽商科大学数学の対策を解説します。
最新の入試情報はここから!:国立大学法人 北海道国立大学機構 小樽商科大学
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
小樽商科大学 数学:出題傾向と特徴
- 試験時間・問題数・形式
- 試験時間は 100分 程度。
- 大問は 5題構成 が基本。
- 形式は 記述式 で、小問集合を含む大問が存在する。
- 第1問・第3問は小問集合(複数の小問を並べた形式)で構成されることが多い。 - 出題範囲・テーマ傾向
- 第一群/第二群方式:要項には「数学の第一群は、数学Ⅰ・Ⅱ・A 全範囲+数学B(数列)+数学C(ベクトル)」を出題範囲とする旨が明記されている。第二群にはそれに加えて「数学Ⅲ、複素数平面・平面上の曲線」なども含めるという扱い。
- 関数分野(特に指数・対数・二次関数・対数関数など)は必ず出題されやすく、重点分野とされている。
- 微分・積分は頻出。特に数Ⅲの積分法(面積・体積問題など)が、5番目など終盤の大問で出題されやすい。
- 小問集合では、図形・二次関数・数列など教科書レベルの標準テーマが扱われることが多い。
- 過去問例では、文系数学出題で、大問1に「データ分析(数学Ⅰ)」、そのほか「図形と方程式(数学Ⅱ)」「確率(数学A)」などが含まれていた例あり。 - 難易度・傾向
- 全体として「教科書~標準レベル」が中心。ただし、終盤の大問に難度を上げるタイプが混ざることがある。
- 計算量がやや多めの設問が出る年もあり、式変形・処理力が試される。
- 作者や年度によって出題スタイルにばらつきがあるという受験分析も見られる。
特徴
特徴・注意点
- 出題範囲が「第一群・第二群」に分かれていて、志願者がどちらを選ぶかで問われる範囲が変わる。
- 小問集合で複数単元を横断する問題があり、テーマがバラエティに富む。
- 終盤の問題で数Ⅲの内容を問う設問が定番化する傾向。
- 誘導型問題(ステップ式)を利用する大問も多く、導かれた設問を使って本問題にたどり着く構成。
- 部分点を取るため、途中過程・論理記述を丁寧に書くことが重要。
📚 分野別対策に最適!おすすめ参考書2選
小樽商科大学の数学で特に重要な「関数」と「微分積分」の対策を強化するための参考書を厳選しました。この参考書を始める前に、基礎重視の参考書、網羅系参考書で基礎を固めておきましょう。(青チャートなど)
1. 関数対策:「理系数学 入試の核心 標準編」
分野: 関数全般(二次関数、指数・対数関数など)
小樽商科大学の数学では、まず大問として出題されることの多い関数分野で確実に得点することが重要です。この「入試の核心 標準編」は、標準的な難易度の良問が厳選されており、多岐にわたる関数の応用問題を効率よく演習できます。基礎的な知識を、入試で求められる論理的な解答へとつなげるための橋渡しとして最適です。関数の応用力を固め、得点源とするために役立ちます。
2. 微分積分対策:「数学III スタンダード演習」
分野: 微分積分(特に数IIIの積分法)
さらに、合否を大きく左右する微分積分、特に数IIIの積分法は、毎年大問として出題される傾向があります。この「数学III スタンダード演習」は、数IIIの微分積分の応用的な計算力と論証力を鍛えるのに適しています。標準的な問題からやや難度の高い問題までバランス良く収録されており、入試本番で要求される粘り強い思考力と正確な記述力を養うことができます。微分積分で差をつけたい受験生に特におすすめの一冊です。
これらの参考書で頻出分野の応用演習を重ね、過去問演習へと移行することで、小樽商科大学 数学の合格に近づくでしょう。
小樽商科大学 数学対策 Q&A
Q1. 基礎固めを終えた後、最初に取り組むべきことは何ですか?
A1. 基礎的な問題集を一周し終えたら、まず、過去問を1年分だけ解いてみましょう。これは実力を測るためではなく、出題形式や時間配分、記述の要求レベルを肌で感じることが目的です。したがって、この段階で点数が取れなくても気にする必要はありません。
Q2. 小樽商科大学の数学で、特に力を入れるべき分野はありますか?
A2. はい、やはり、微分積分と関数全般に重点を置くべきです。特に数IIIの積分法は、ほぼ毎年大問で出題されるため、集中的に対策が必要です。そのうえ、二次関数や指数・対数関数など、関数に関する応用問題も頻出ですから、幅広い演習が不可欠です。
Q3. 微分積分の対策で、計算ミスを減らすにはどうすれば良いでしょうか?
A3. 計算ミスは、練習量が足りないか、解答の途中式を省略しすぎていることが主な原因です。そこで、日々の演習では、検算や途中式の書き方に注意を払いましょう。さらに、入試本番を想定し、時間を計って計算ドリルを行うなど、計算速度と正確性を両立させる訓練も有効です。
Q4. 記述式試験で、部分点を取るために意識すべきことはありますか?
A4. もちろんあります。なぜなら、大学入試の記述では、論理の一貫性と数学的表現の正確さが評価されるからです。単に答えが合っていても、過程が飛躍していると減点されます。したがって、「定義域の確認」や「図を書いて考察したこと」など、解答に至るまでの思考の筋道を丁寧に記述することを心がけましょう。
Q5. 共通テストと二次試験の対策を、どのように並行させれば良いですか?
A5. 共通テスト対策は、基本的に夏までに基礎力を固める段階で自然と並行できます。しかし、共通テストの形式に慣れるための対策は、秋以降に過去問や予想問題を利用して集中的に行うのが効率的です。その結果、二次試験対策で養った記述力や応用力が土台となり、共通テストの点数も安定しやすくなるでしょう。
小樽商科大学 数学の「落とし穴」ポイント
1. 記述式の「途中省略」という落とし穴
まず、小樽商科大学の数学は記述式である、という点を軽視してはいけません。マーク式の試験では答えさえ合っていれば満点ですが、記述式ではそうはいきません。したがって、普段の学習から、途中式や論理の流れを省略しすぎると、本番で「答えは合っているのに部分点がもらえなかった」という事態に陥ります。なぜなら採点者はあなたの頭の中ではなく、答案に書かれた内容でしか評価できないからです。そこで、「なぜそうなるのか」を論理的に説明する練習を怠らないようにしましょう。
2. 数III「積分法」を軽視する落とし穴
さらに、小樽商科大学は文系学部ですが、数学では数IIIの積分法が出題されることが大きな特徴であり、多くの文系受験生にとっての「落とし穴」となります。そのため、「文系だから数IIIは不要」と決めつけたり、対策を後回しにしたりすると、他の受験生に大きく差をつけられてしまいます。しかも、この分野はほぼ毎年大問として出題される傾向が強いため、全体の得点に占める割合が非常に高いです。したがって、苦手意識を持たず、標準的な積分計算と面積・体積などの典型的な応用については、時間をかけて習得する必要があります。
3. 関数分野の「網羅不足」という落とし穴
また、頻出分野である関数について、二次関数だけ、あるいは三角関数だけなどと偏った対策をしてしまうのも危険です。というのは、小樽商科大学の入試では、二次関数に加えて指数・対数関数や様々なタイプのグラフの考察など、幅広い分野から出題されるためです。それゆえ、特定の関数だけを深くやるのではなく、多様な関数について、定義域、値域、最大・最小、グラフの概形といった基本事項を網羅的に復習することが重要です。応用問題に対応するためには、分野をまたいだ知識の結合も求められます。
小樽商科大学 数学 対策の最終まとめ
したがって、小樽商科大学の数学で合格を勝ち取るためには、入試の傾向を正確に把握し、戦略的な学習を行うことが何よりも重要です。
まず、難易度は標準レベルが中心である反面、記述式の答案作成力が合否を分けます。そこで、普段から論理的な思考過程を丁寧に書く練習を徹底してください。
そして、学習の核となるのは、毎年頻出する関数と、文系受験生にとっての難関である数IIIの積分法を含む微分積分です。なぜなら、これらの分野は配点が高く、差がつきやすいからです。さらに、紹介したような良質な標準・応用問題集を繰り返し解き、知識の網羅性と応用力を同時に高めましょう。
これらの対策を積み重ねることで、小樽商科大学 数学の試験で安定して高得点を獲得し、栄冠を手にすることができるでしょう。皆さんの粘り強い努力を応援しています!
小樽商科大学全体の勉強法はこちら!
小樽商科大学編:小樽商科大学勉強法|1年間で逆転合格
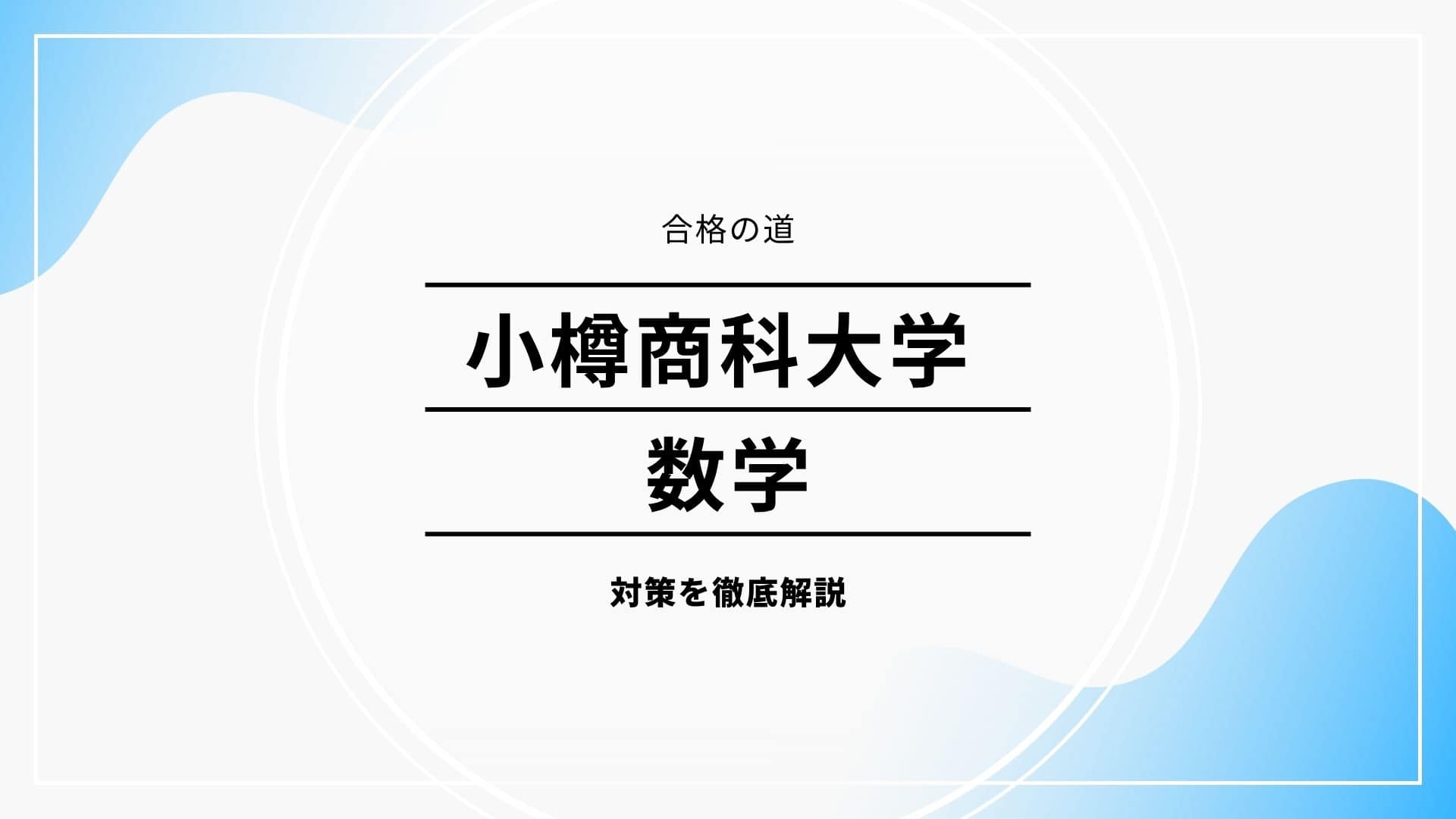
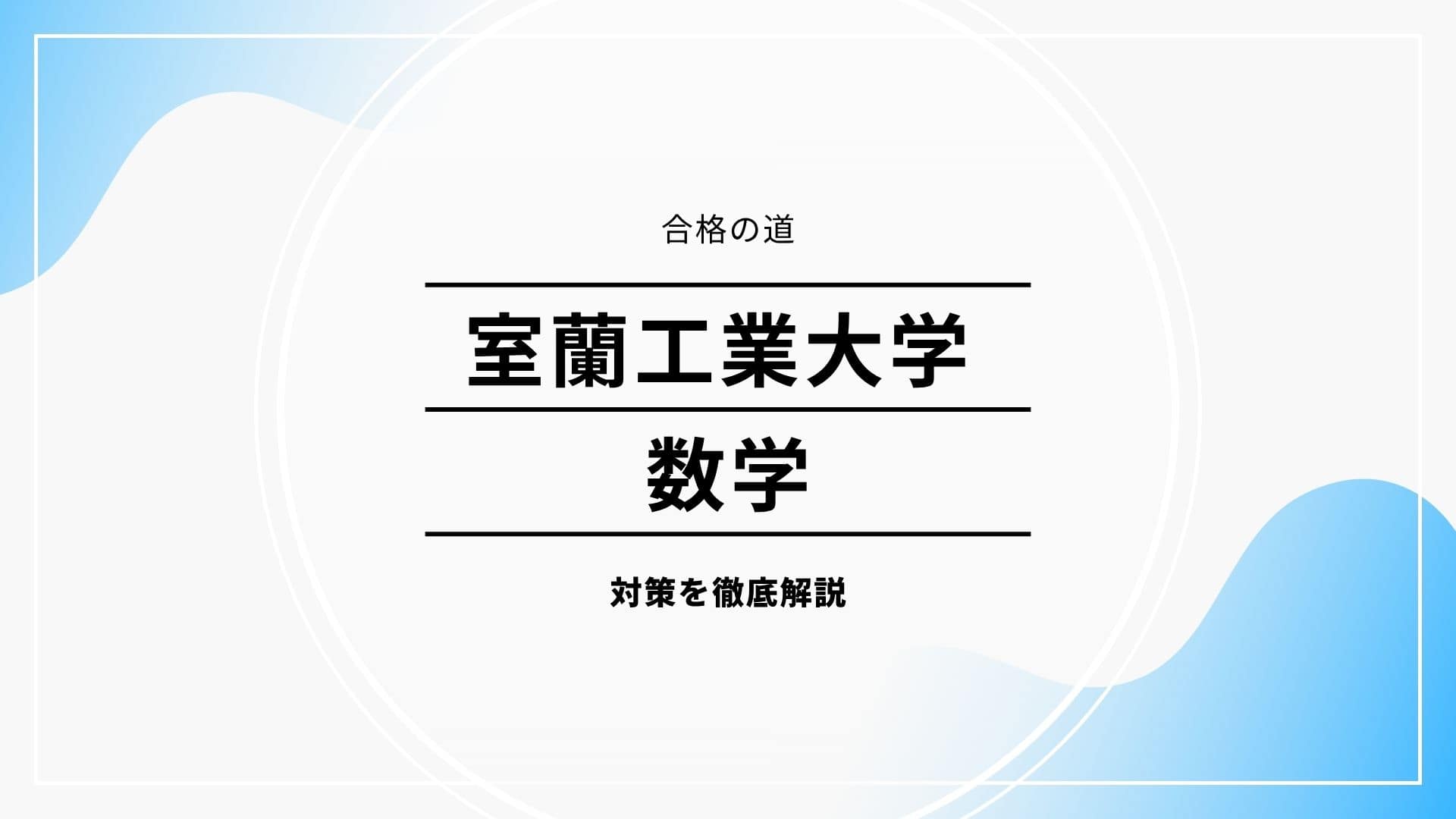
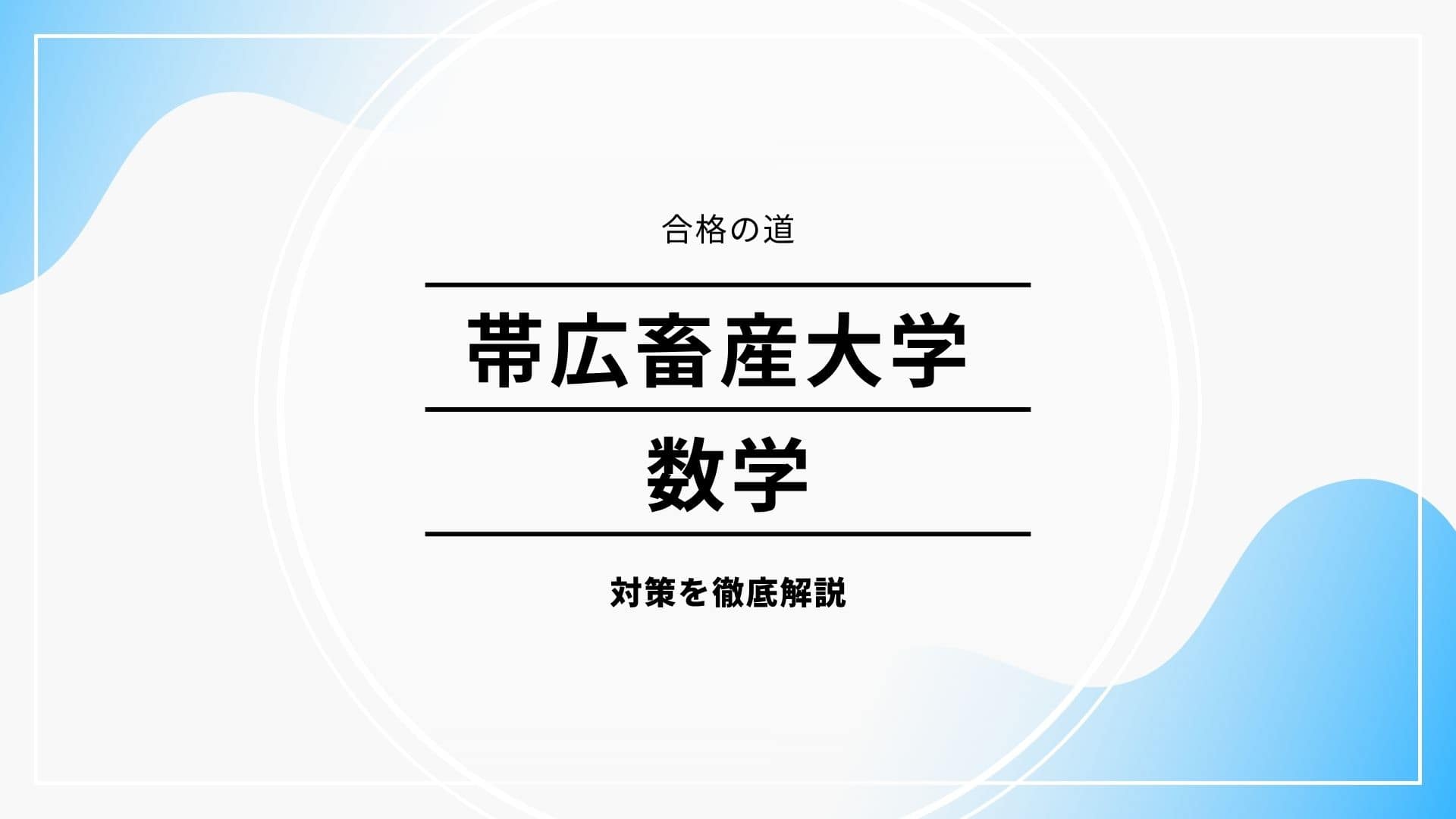
コメント