近年、情報系の人気が高まる中、電気通信大学を志望する受験生にとって、合否を大きく左右するのが数学です。この最重要科目を攻略せずに合格はありえません。そこで、この記事では、電気通信大学 数学 対策に焦点を当て、その出題傾向から具体的な学習法まで、あなたの疑問を一気に解決します。さらに、記述式試験で高得点を取るための秘訣も公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
最新の入試情報はここから!:国立大学法人 電気通信大学
電気通信大学 数学の出題傾向・特徴
- 大問4題構成・全問記述式 が基本形式。
- 試験時間は 前期:120分、後期では時間延長の年もある。
- 数学Ⅲ・微分・積分 からの出題割合が高い。
- 頻出テーマ:数列、ベクトル、複素数平面なども多く出題される。
- 問題は 誘導小問を多く含む形式 が多く、段階的な問いが組み込まれている。
- 難易度は「標準〜やや発展」で、奇問・極端な難問は少ない傾向。
- 計算量が多め、ミスの影響が大きいため計算力・正確性が重視される。
おすすめ参考書:分野別対策
この参考書を始める前に、基礎重視の参考書、網羅系参考書で基礎を固めておきましょう。(青チャートなど)
1. 【計算力・スピード対策】: 合格る計算 数学Ⅲ
まず、電気通信大学の数学において、特に合否を分けるのが数Ⅲ(微積分)の計算力です。なぜなら、出題される問題は計算量が非常に多く、計算ミスや時間ロスが命取りになるからです。
そこで、この分野の対策として強くおすすめするのが、『合格る計算 数学Ⅲ』です。この参考書は、数学Ⅲの複雑な計算に特化しており、「どうすれば早く正確に解けるか」という計算のテクニックとノウハウを徹底的に解説しています。したがって、過去問演習と並行してこれに取り組むことで、解答スピードと正確性を劇的に向上させることができます。
2. 【応用力・実戦力対策】: 理系数学の良問プラチカ
次に、基礎的な知識と計算力を身につけた受験生が実戦力を養うために必要なのが、良質な応用問題への挑戦です。
そのため、『理系数学の良問プラチカ』をおすすめします。この問題集には、標準から応用レベルの良問が厳選されており、電気通信大学 数学の頻出分野であるベクトルや数列などを網羅的に演習できます。さらに、記述式の答案作成に求められる論理的思考力や、初見の問題への対応力を効率よく鍛えることが可能です。このように、計算力を『合格る計算』で磨きつつ、応用力を『プラチカ』で養うという両輪の対策が、合格への確実な道となります。
電気通信大学 数学 対策Q&A
Q1. 電気通信大学の数学は、どの分野を重点的に対策すべきですか?
A. まず、数学Ⅲからの出題、特に微積分が最も重要です。配点の大部分を占め、計算量も多いため、この分野を最優先で完璧にすることが必須です。さらに、数列やベクトル、複素数平面も頻出ですから、これらも手厚く対策しましょう。
Q2. 記述式試験で高得点を取るためのポイントは何ですか?
A. もちろん、最終的な答えが合っていることが大前提です。しかしながら、電気通信大学の数学は全問記述式なので、解答に至る論理的な過程を採点者に分かりやすく示すことが重要になります。したがって、計算ミスをしないことはもちろん、途中の式や考え方を省略せずに丁寧に書くことを心がけてください。
Q3. 計算量が多いと聞きましたが、時間配分のコツはありますか?
A. 確かに、試験時間120分に対して計算量が多いため、時間配分は非常に重要です。そこで、過去問を解く際は、本番と同じ時間(120分)で取り組み、各大問にかける時間をあらかじめ決めておきましょう。そして、途中で計算に詰まったらすぐに次の大問の基本問題に移るなど、時間切れにならないよう柔軟に対応する練習が必要です。
Q4. 基礎問題集を終えた後、次に進むべき参考書は何ですか?
A. 基礎が固まったら、次に実戦的な応用力を養う必要があります。そのため、電気通信大学の出題レベルに合致した『理系数学の良問プラチカ』のような、標準から応用へ橋渡しをする問題集に進むのが良いでしょう。加えて、計算力に不安があるなら『合格る計算 数学Ⅲ』などで、計算スキルを並行して磨いてください。
Q5. 過去問はいつから、何年分やるべきでしょうか?
A. 一般的に、直前(12月頃)から本格的に取り組む受験生が多いです。ただし、電気通信大学の数学は出題傾向が一定しているため、早めに傾向を掴むことが有利です。したがって、基礎固めが終わった段階(夏休み以降)で一度手をつけ、最低でも5年分を繰り返し解き、出題パターンに慣れておくことを強く推奨します。
電気通信大学 数学 対策の落とし穴ポイント
1. 「計算量」を軽視すること
最も大きな落とし穴は、問題の難易度自体は標準的であることから、「計算量」を軽視してしまうことです。なぜなら、電気通信大学の数学は、特に微積分などの問題で、計算過程が長く複雑になりがちだからです。そこで、日頃から解答用紙の余白を意識し、丁寧かつスピーディに計算を進める訓練が必要です。
2. 「記述」の甘さによる部分点の喪失
次に、全問記述式であるにもかかわらず、答案の「記述」が不十分になることも大きな落とし穴です。もちろん、答えが合っていれば点数にはなります。しかしながら、少しでも計算を間違えた場合、解答の根拠となる論理展開や途中式が不明瞭だと、採点官は部分点を与えられません。そのため、答えだけでなく、用いた公式、計算の道筋、論理の飛躍がないかを常にチェックし、採点者に伝わる論理的な答案を作成することが求められます。
3. 数学Ⅲ以外の「基礎」が揺らぐこと
確かに、数学Ⅲが最重要分野であることは間違いありません。ただし、対策の過程で数学ⅠA・ⅡBの基礎がおろそかになると、応用問題で足元をすくわれます。たとえば、ベクトル、数列、三角関数など、数Ⅲと融合して出題される分野の基本公式や定理があやふやだと、問題文の誘導に乗ることができません。したがって、融合問題に対応できる土台としての基礎力を維持し続けることが大切です。
まとめ
合格の鍵を握る電気通信大学 数学 対策のまとめです。
結局のところ、電気通信大学 数学 対策の成功は、数学Ⅲ(特に微積分)の徹底的な習熟にかかっています。なぜなら、出題の核であり、合否を分ける計算量の多さもここに集約されているからです。このように、基礎固めから応用・記述力強化まで、正しいステップを踏んで対策を万全にし、電気通信大学の合格を掴み取りましょう。
電気通信大学全体の勉強法はこちら!
電気通信大学編:電気通信大学勉強法:戦略的な学習計画
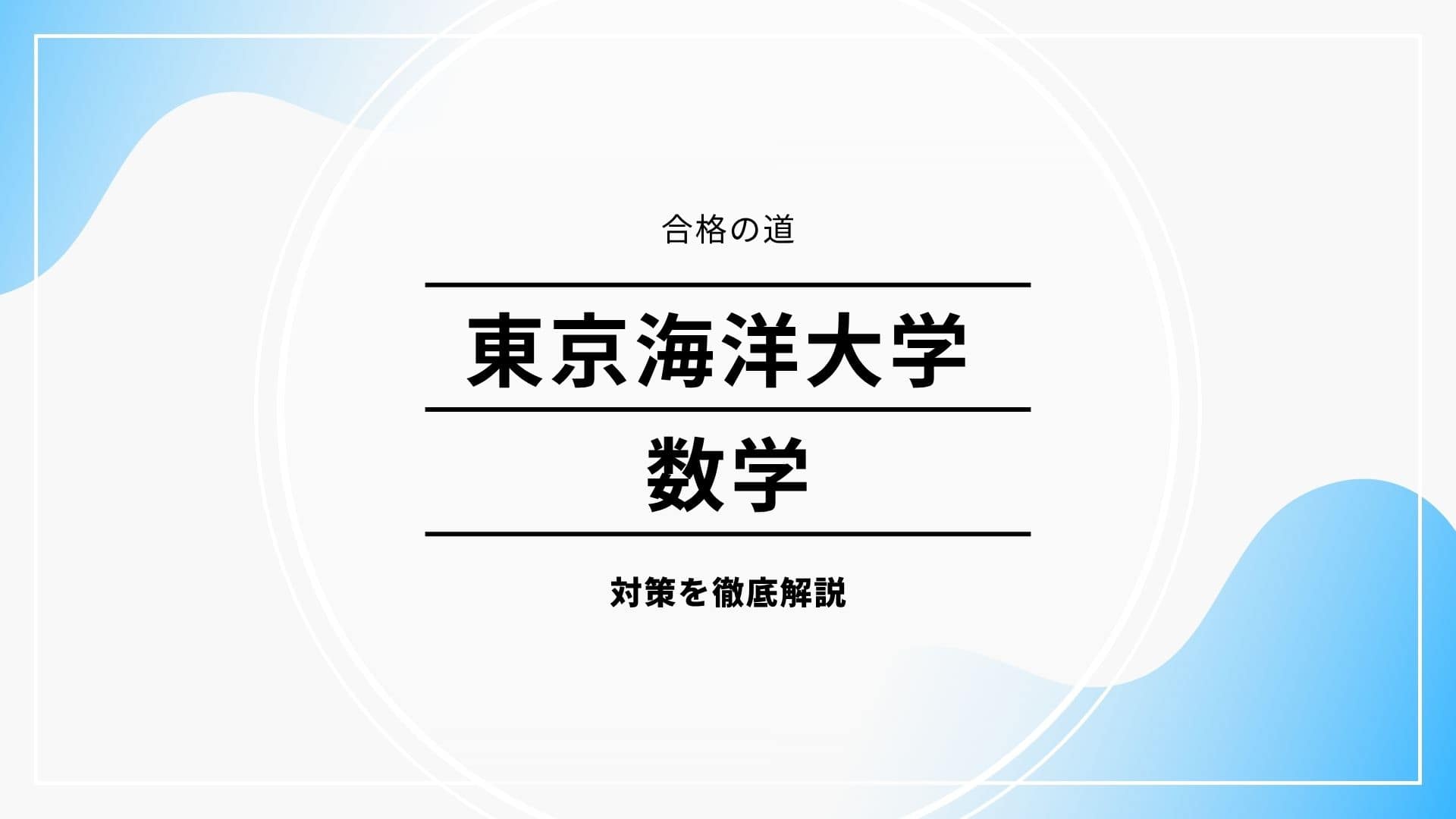
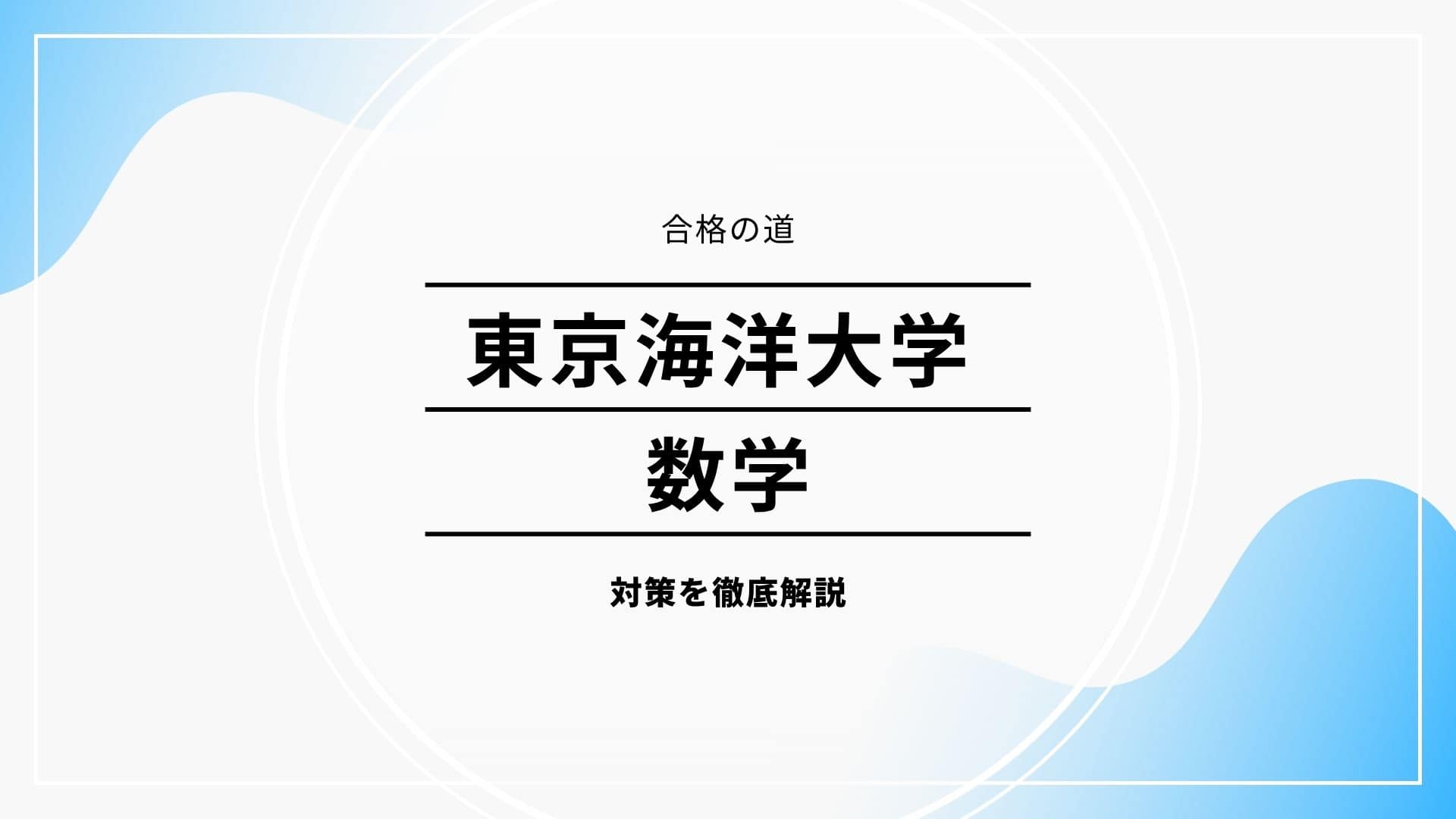
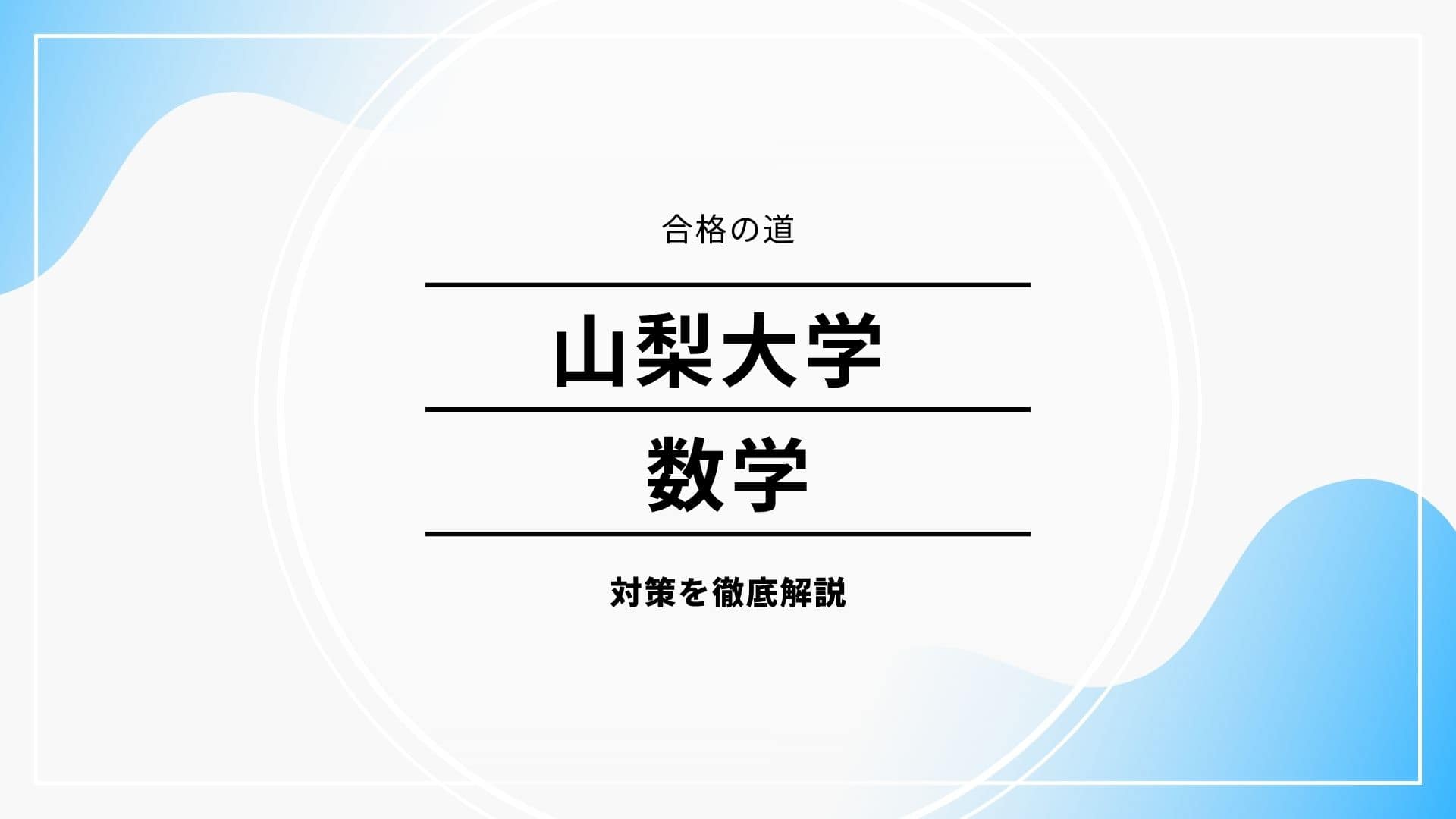
コメント