公立はこだて未来大学の受験を控える皆さん、「数学で高得点を取れるか不安…」と感じていませんか?
しかし、ご安心ください!
本記事では、システム情報科学部の出題傾向に基づいた効率的かつ効果的な対策法を徹底的に紹介します。具体的には、基礎の徹底から過去問演習、時間配分のコツまで、合格に直結するノウハウを余すところなくお伝えします。
したがって、この対策を実行することで、あなたの数学の得点力は飛躍的に向上するでしょう。さあ、一緒に未来大合格への道を切り開きましょう!
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
最新の入試情報はここから!:公立はこだて未来大学 -Future University Hakodate-
出題範囲・形式
- 個別学力検査(2次試験)で数学が出題され、配点300点という情報があります(数学300点、英語200点など)。
- 問題構成として、必須問題+選択問題という形式が定められています。
- 出題範囲:必須問題は「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」の範囲。選択問題では「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C または 数学Ⅲ・C」から選択。
- 解答形式は記述式、途中式・論理・理由などを書く設問があります。
- 教科書範囲を基盤としつつ、選択問題で“応用力・総合的な思考”を問う傾向があります。
出題傾向・特徴
- 必須問題では基礎的事項が中心—例えば数学B「数列」や数学C「ベクトル」が明記されています。
- 選択問題では、数学ⅡBまでの範囲の選択(例えば数Ⅱの微分・積分、数B数列)または数学Ⅲ・Cを含めた範囲選択が可能であり、志望者のレベル/得意分野に応じて問題を選べる構成です。
- 教科書レベルの典型問題が多く、まず基礎を確実に固めたうえで、過去問演習を通じて誘導・論証・記述の練習を重ねる必要があるという対策案があります。
- 出題範囲に “抜け” がないよう準備することが推奨されており、数Ⅰ~数Ⅲ・A~Cまで幅広く対応できるようにすることが重要という指摘もあります。
対策ポイント
- 「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」の基礎事項を確実に理解・定着させることが最優先。特に必須問題で問われる範囲です。
- その上で、「数列」「ベクトル」といった数学B・数学Cの単元を重点的に演習。
- 選択問題レベルを意識して、数学Ⅲ/Cを含む範囲にも準備しておくと安心です。
- 解答において、途中式・変形の理由・論理的説明を丁寧に書けるよう、記述式答案の練習を。
- 過去問を使って「問題構成(必須+選択)」「どの分野が出たか」「選択問題でどのタイプを選ぶか」を分析し、戦略を立てる。
- 基礎が大半を占めるため、巧妙な難問にこだわるより「確実に得点できる典型+記述力」の向上が合格の鍵、という意見があります。
おススメ参考書まとめ
下の参考書を始める前に、基礎重視の参考書、網羅系参考書で基礎を固めておきましょう。(青チャートなど)
実戦演習・応用力強化用(理系数学全般)
オススメ: 『理系数学の良問プラチカ 数学I・A・II・B・C』
接続語: 基礎が固まったら、次に得点力を上げるための応用演習が必要です。そこで、『理系数学の良問プラチカ』を推奨します。これは、入試標準〜応用レベルの質の高い良問が揃っており、思考力と記述力を鍛えるのに最適です。未来大のやや難しめの問題にも対応できる力が身につきます。
3. 分野特化・演習量確保用(理系数学、特にII分野の対策)
オススメ: 『良問の風 理系数学①』
接続語: さらに、特定分野の演習量を増やしたい場合や、プラチカよりももう少し難易度が穏やかな問題から始めたい場合は『良問の風』が役立ちます。このシリーズは物理の参考書が有名ですが、数学にもあり、頻出の典型問題を中心に構成されており、確実な定着を図ることができます。特に数IIなどの重点分野で、解法の手順を固めるのに効果的です。
💡 公立はこだて未来大学 数学対策Q&A
Q1. どの分野が特に出題されやすいですか?
A1. まず、システム情報科学部では、数学II・B、特に微分積分とベクトルが頻出です。また、理系受験者は数学IIIの微分積分や複素数平面からの出題も多く、対策が必須です。
Q2. 共通テストと二次試験の難易度差はどれくらいですか?
A2. 確かに、共通テストは基礎的な知識を幅広く問う形式ですが、それに対して、二次試験は応用力と論述力を試す問題が多く、難易度が上がります。特に記述式の解答を意識した対策が必要です。
Q3. 数学の対策はいつから始めるべきですか?
A3. 理想としては、高校3年生の夏休みまでに全範囲の基礎固めを終えるべきです。なぜなら、秋以降は過去問演習や応用問題への取り組みが必要になるからです。
Q4. 過去問演習はいつ頃から、どのように取り組むのが効果的ですか?
A4. したがって、基礎が固まった秋(10月頃)から過去問演習を本格的に始めましょう。ただし、単に解くだけでなく、制限時間内に完答できるか、記述方法が適切かを意識して取り組み、間違えた問題は必ず解説を読んで理解を深めてください。
Q5. 記述で点数を取るためのコツは何ですか?
A5. まず、解答に至る論理の流れを明確にすることが重要です。さらに、途中の計算式や用いた定理・公式を省略せず、採点者に伝わるよう丁寧に記述する癖をつけましょう。部分点を確実に取りにいく意識が大切です。
⚠️ 公立はこだて未来大学 数学の落とし穴
- 計算ミスを軽視すること
- まず、未来大の数学は平易な問題から応用を問う問題まで出題されますが、どれも記述量が多くなりがちです。したがって、基本的な計算ミスが命取りになります。そのため、日頃から検算の習慣をつけ、丁寧な計算を心がけることが重要です。
- 証明・論述の対策不足
- また、単に答えを出すだけでなく、解答の過程を論理的に記述する力が求められます。しかし、多くの受験生が計算練習に時間を割き、証明や論述の練習を疎かにしがちです。模範解答を写すだけでなく、自分の言葉で論理を組み立てる訓練を積んでください。
- 大問選択の時間配分ミス
- さらに、大問で選択問題があるため、どの問題を選ぶか、そしてその問題にどれだけの時間を割くかの判断が非常に重要です。そこで、過去問演習の際、解く大問の組み合わせと時間配分を常に意識してシミュレーションしておかないと、本番で焦ってしまい、高得点を逃すことになります。
公立はこだて未来大学 数学で合格を掴むための最終戦略
結論として、公立はこだて未来大学の数学で合格を確実にするには、「基礎固め」と「記述対策」のバランスが鍵となります。したがって、土台を築き、さらに『理系数学の良問プラチカ』などの良問演習で応用力と論述力を徹底的に磨き上げてください。
そこで、計算ミスや論述の甘さといった落とし穴を避け、過去問で時間配分をシミュレーションすることが極めて重要です。なぜなら、未来大の入試は、正確な知識と論理的な思考過程を丁寧に伝える記述力が求められるからです。
さあ、本記事で紹介した対策を実践し、自信を持って未来大合格を勝ち取りましょう!
全体の勉強法はこちら!
公立はこだて未来大学編:公立はこだて未来大学に受かる1年間の勉強法
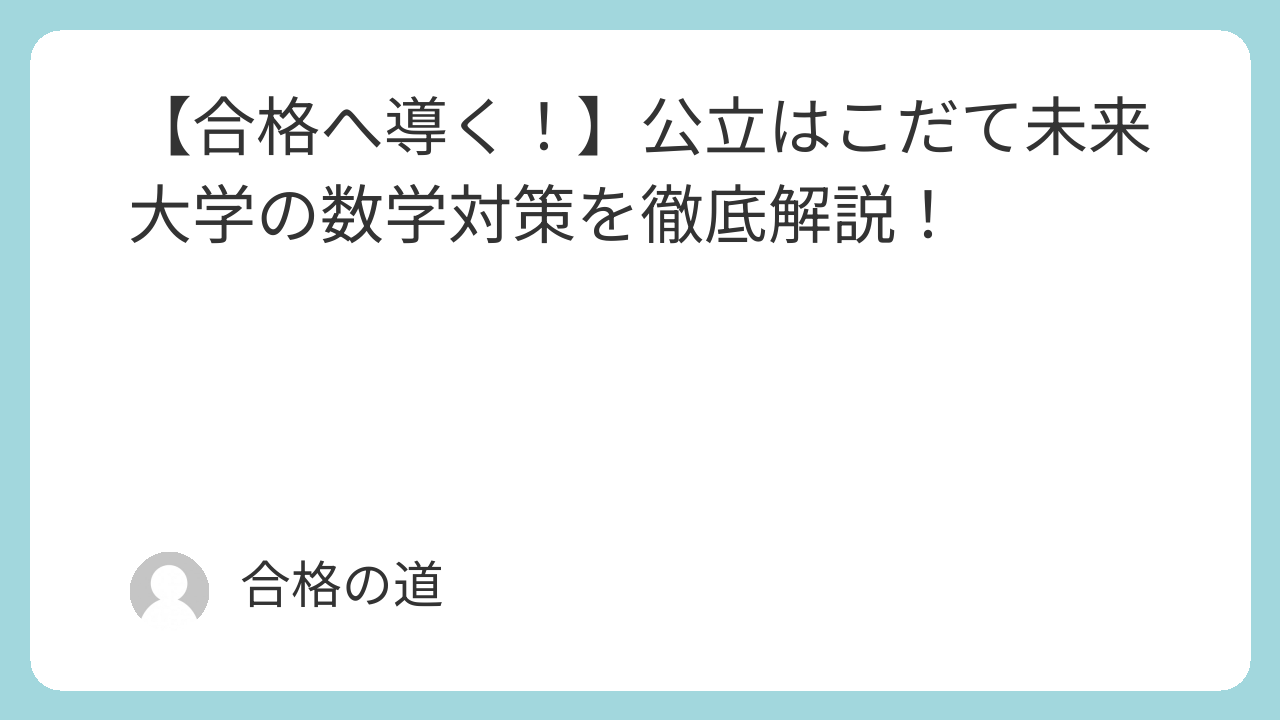
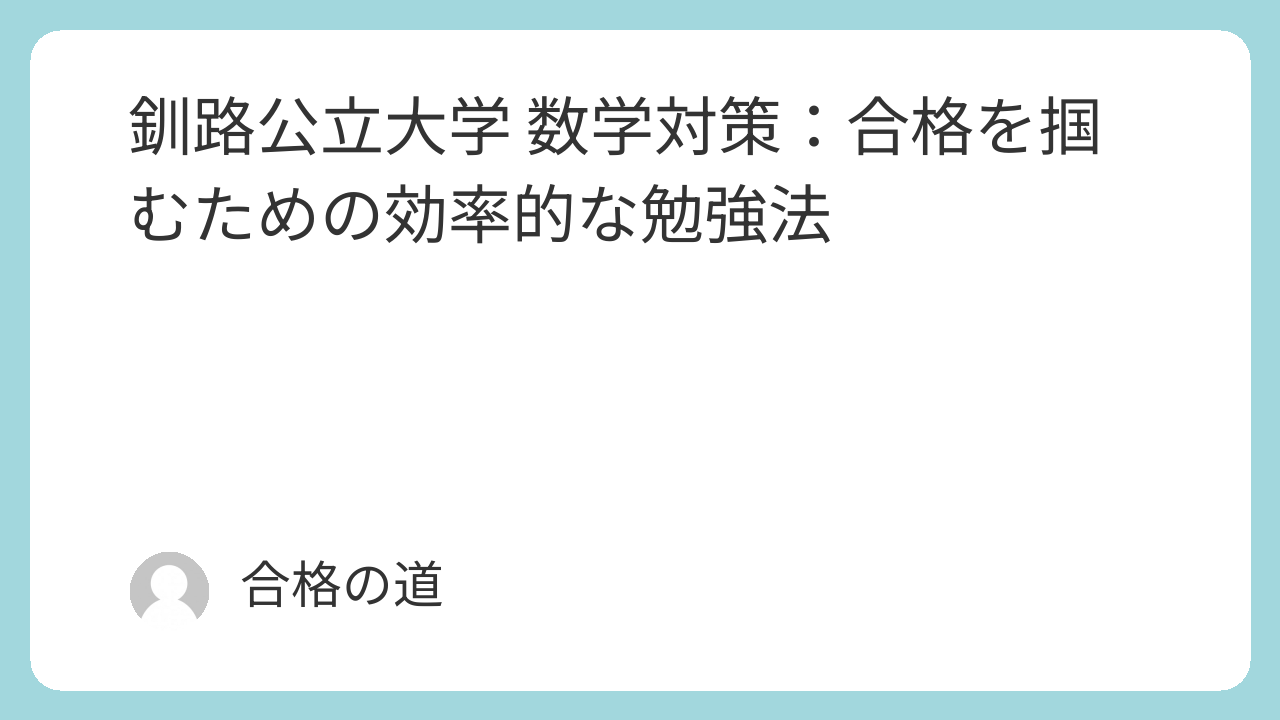
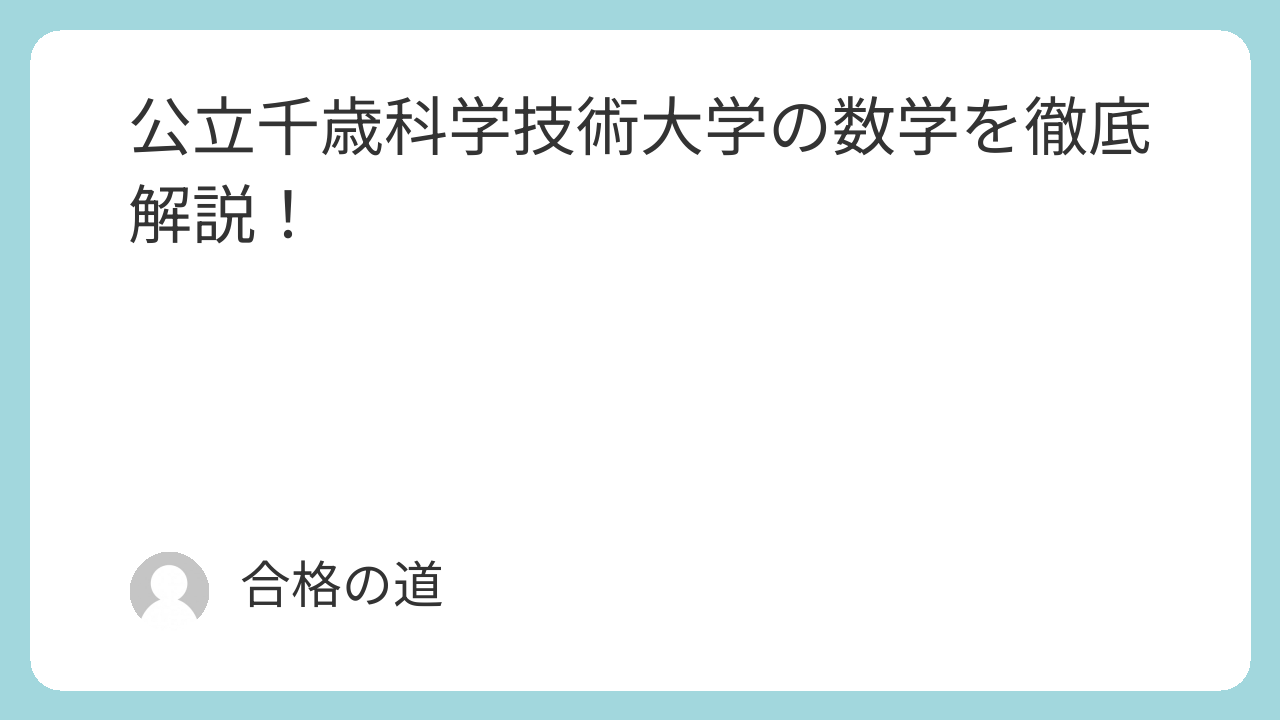
コメント