東京都立大学の数学で高得点を目指すには、出題傾向を正確に把握し、効率的な対策を講じることが不可欠です。そこで、本記事では、文系・理系それぞれの対策と具体的な学習法を簡潔にまとめました。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
最新の入試情報はここから!:東京都立大学
文系数学
出題形式・構成
- 記述式で出題され、例年大問4題構成とされています。
- 試験時間はおおよそ90分。
出題範囲・傾向
- 高校数学Ⅰ・Ⅱ・A・Bおよびそれらに準じる範囲から幅広く出題。
- 頻出テーマとして「整数」「数と式」「三角関数」「数列・漸化式」「微分・積分」が挙げられています。
- また、証明・記述力を問う設問の出題率も高くなってきています。
難易度・特徴
- 難易度は「標準~少し易しめ」くらいとされており、教科書的な問題を確実に解けることが前提。
- 時間配分がタイトなため、典型的な問題を素早く処理する練習が有効です。
理系数学
出題形式・構成
- 記述式出題。理系では大問3題構成が典型。
- 特に、学部・学科によっては「共通問題+独自追加問題」があるケースも。
- 試験時間は75分程度とされることもあります。
出題範囲・傾向
- 高校数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bの広範囲が対象。特に「数学B・数学Ⅲ(数列・ベクトル・微分積分)」からの出題が目立ちます。
- 頻出分野としては「微分積分法」「数列・漸化式」「ベクトル」「複素数平面」「図形(平面・立体・グラフ)」などです。
難易度・特徴
- 難易度は「標準~やや難」レベル。典型問題が中心ながら、しっかりした思考や記述力・計算力が問われます。
- 誘導は比較的丁寧なものの、計算量が多め・証明問題の比率も上がっているため、ミスを減らす訓練が重要です。
📚 東京都立大学 数学 対策におすすめの参考書
東京都立大学の数学は、基礎の確実な理解を前提とした標準からやや難レベルの応用力と正確な記述力が求められます。この要求に応えるため、難易度を段階的に上げる以下の2冊がおすすめです。
下の参考書を始める前に、基礎重視の参考書、網羅系参考書で基礎を固めておきましょう。(青チャートなど)
1. 理系数学対策:やさしい理系数学
理系数学で合格点を確保するためには、数IIIを含む応用問題への習熟が不可欠です。
まず、基礎的な解法パターンを一通り習得した後、この「やさしい理系数学」に取り組みます。なぜなら、この問題集は、難しすぎる問題は避けつつ、入試で頻出する良質な標準〜応用レベルの問題が厳選されているからです。したがって、東京都立大学の理系数学で求められる確かな実力を効率よく養うことができます。特に、微分積分や数列、ベクトルといった頻出分野に集中的に取り組み、論理的な思考プロセスを確立することが重要です。
2. 文系数学対策:文系数学の良問プラチカ
文系数学で高得点を狙うには、標準問題を素早く正確に処理し、証明問題にしっかりと対応できる力が求められます。
そこで、基本が定着した次に、この「文系数学の良問プラチカ」で実戦的な演習を積むのが良いでしょう。この問題集は、文系受験生が解くべき質の高い良問が揃っており、応用力を無理なく引き上げることができます。加えて、都立大で頻出の論述や証明を含む問題を通じて、採点者に伝わる解答を制限時間内に完成させる記述力を徹底的に鍛えることができます。
東京都立大学 数学対策 Q&A
Q1. 基礎固めはいつまでに完了させるのが理想的ですか。
A1. 東京都立大学の数学は、基礎を応用する力が問われます。そのため、高校3年生の夏休み、具体的には8月末頃までに、教科書に載っている基本知識と、網羅系参考書(青チャートなど)の標準的な問題を一通り習得しておくことが望ましいです。なぜなら、秋からは共通テスト対策や応用問題の演習に時間を充てる必要があるからです。
Q2. 理系数学の学習において、特に重点を置くべき分野はどこですか。
A2. 理系数学で合格点を確実にするには、数学IIIの「微分積分」に最も力を入れるべきです。これに加え、「数列」「ベクトル」「複素数平面」も頻出傾向にあります。特に微分積分は出題の中心であり、計算量が多くなりがちです。したがって、計算練習を多くこなし、複雑な問題を迅速かつ正確に処理する能力を身につけておくことが重要です。
Q3. 文系・理系共通で、記述問題の対策において意識すべきポイントは何ですか。
A3. 都立大の数学はすべて記述式であり、記述対策で最も重要なのは「論理が一貫していること」です。つまり、最終的な答えだけでなく、解答に至るまでの思考過程が、採点者に誤解なく伝わるように記述されているかを確認する必要があります。そのため、過去問を解いた後は、模範解答を参照して、自分の記述が論理的に十分であったかを検証する作業を繰り返してください。
Q4. 過去問演習を始める適切な時期はいつ頃ですか。
A4. 過去問演習は、本格的な出題傾向を把握し、試験の時間配分に慣れるためにも、秋(9月〜10月)頃から開始するのが効果的です。ただし、全範囲の学習が終わっていなくても問題ありません。最初の数回は時間を厳密に計らずに傾向を分析することに重点を置き、直前期に入ってから、本番を想定した時間配分で解く練習に切り替えていくのが良いでしょう。
Q5. 数学が苦手な受験生は、どのようなステップで学習を進めるべきですか。
A5. 数学に苦手意識がある場合は、いきなり難度の高い問題集に進むべきではありません。まずは、教科書や非常に易しい参考書を使って、基本公式や定理の定義を完全に理解し、基本的な計算を間違えずにできる土台を固めることが最優先です。基礎が固まった後、徐々に網羅系参考書へとステップアップしていくことが、結果的に実力向上の近道となります。
東京都立大学 数学対策の落とし穴
1. 記述の「論理の飛躍」
東京都立大学の数学は全問記述式です。したがって、答えがあっているだけでは不十分です。なぜなら、採点では解答に至るまでの論理的な思考過程が重視されるからです。そのため、計算過程や結論への導き方で論理の飛躍があると大幅な減点につながるため、解答は丁寧に、かつ厳密に記述する訓練が必要です。
2. 理系 数IIIの「計算ミス」
理系数学では、頻出である微分積分を中心に、計算量が非常に多くなります。しかし、試験時間は限られています。したがって、複雑な計算を焦りながら進めることで計算ミスを誘発しやすいのが大きな落とし穴です。そこで、日頃から計算ドリルなどを活用し、速さと正確さの両立を目指した演習を意識的に行う必要があります。
3. 証明問題への「慣れ不足」
文系・理系ともに、証明問題の出題頻度が高いのが都立大の特徴です。そのため、単に答えを出す問題ばかり解いていると、論理的な構造を組み立てて記述する力が不足しがちになります。そこで、過去問や良問集を通じて、数学的帰納法なども含めた証明のパターンと、それを採点者にわかりやすく伝える記述形式に慣れておくことが必須です。
4. 時間配分の「戦略不足」
問題数に対して試験時間に余裕がないため、時間配分の戦略不足は大きな落とし穴です。特に、難しい問題に固執して時間を浪費してしまうと、解けるはずだった標準的な問題を落とすことになります。したがって、過去問演習の際は、「解ける問題から確実に手をつける」「見切る勇気を持つ」といった戦略的な判断力を磨いておく必要があります。
✅ 東京都立大学 数学 対策の最終まとめ
東京都立大学の数学で合格を掴むためには、まず、教科書レベルの基礎知識を盤石にすることが不可欠です。その上で、文系は「文系数学の良問プラチカ」、理系は「やさしい理系数学」などを活用し、志望学部に合わせた応用力を段階的に高める必要があります。そして、最も重要なポイントは、全問記述式であることに対応した論理的な記述力と証明力の養成です。したがって、過去問演習を通じて出題傾向と時間配分に習熟し、計算ミスや論理の飛躍という落とし穴を避け、本番で実力を最大限に発揮できるよう準備を進めましょう。
全体の勉強法はこちら!
東京都立大学編:東京都立大学合格への道|勉強法とポイント解説 – 合格の道
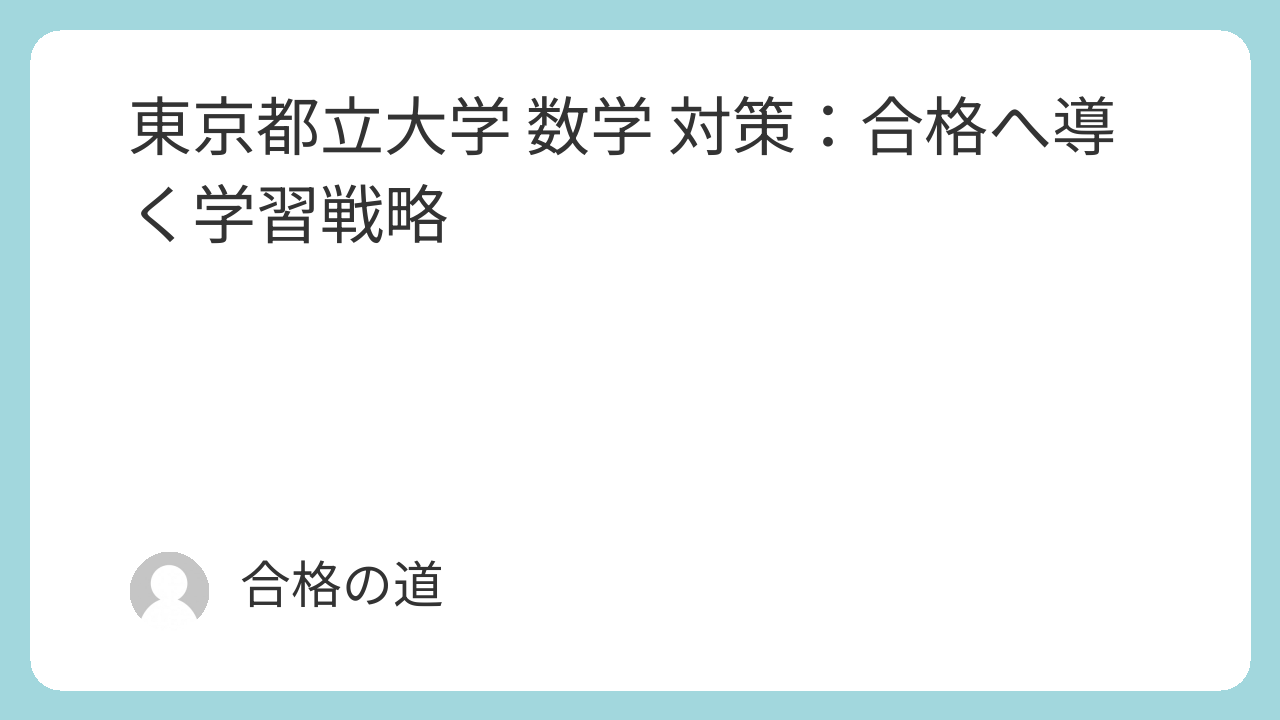
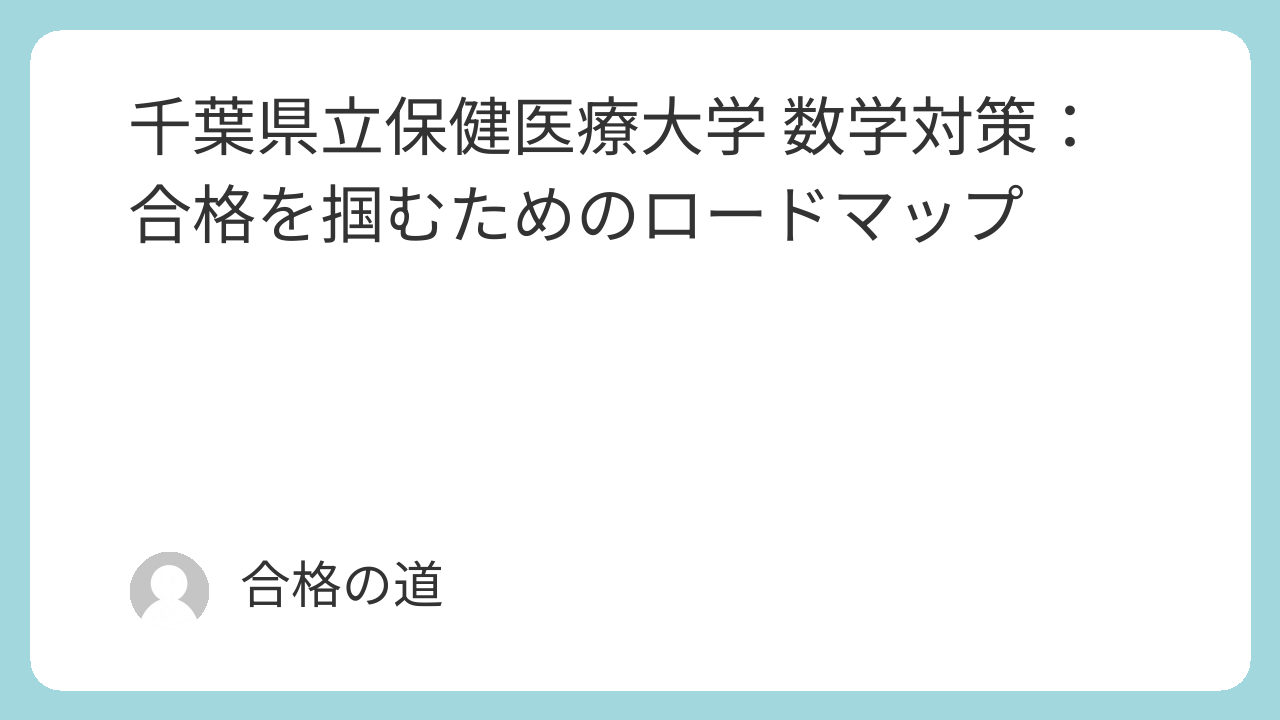
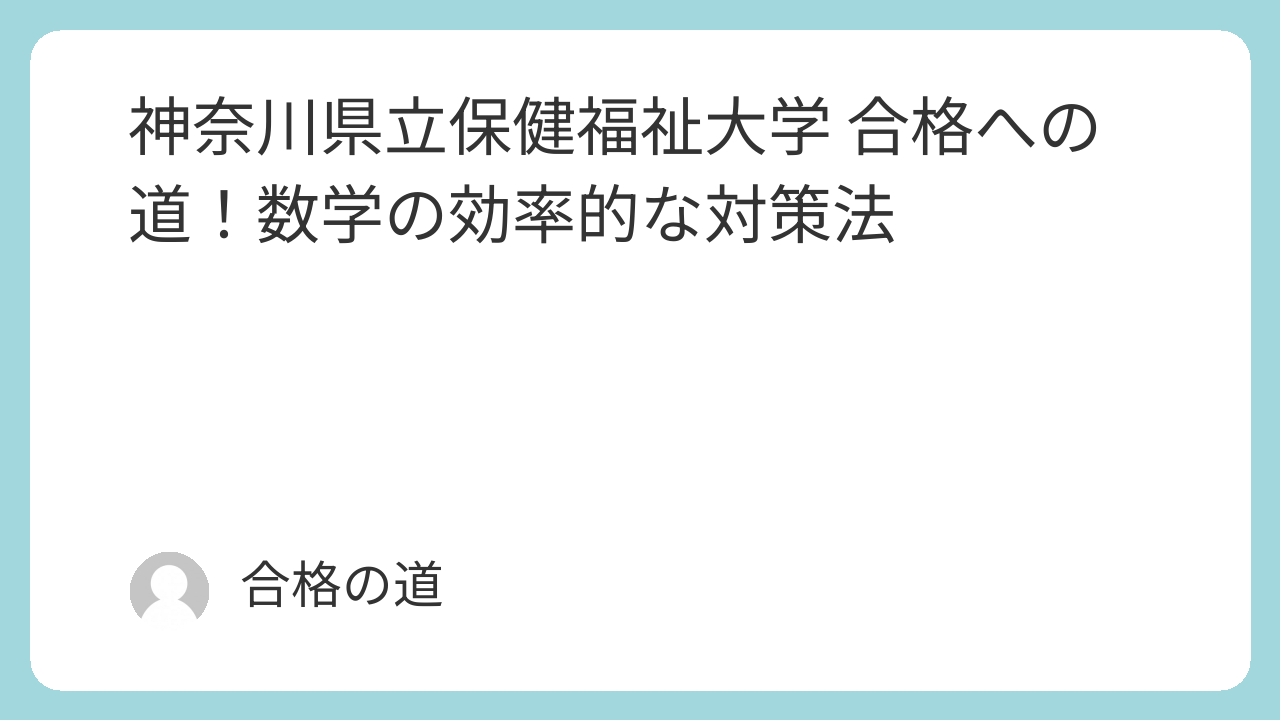
コメント