目次
「東大に合格したい。でも、どんな勉強法が正解なのか分からない。」
そう悩んでいる受験生は、決してあなただけではありません。
実際、「東大 勉強法」で検索しても、情報が多すぎて迷ってしまいますよね。
しかしながら、正しい方法を知り、2年間かけて計画的に取り組めば、合格の可能性は十分にあります。
本記事では、実際に東大に合格した受験生が実践していた勉強法をもとに、
・いつから何を始めるべきか
・どの科目にどう取り組むか
・成績が伸び悩んだときの対処法
など、具体的に解説します。
つまり、「今、何をすべきか」が明確になります。
一方で、ただ長時間勉強するだけでは東大には届きません。
大切なのは、戦略的に学ぶこと。
この記事を読むことで、**あなた専用の「東大合格までの地図」**が見えてくるはずです。
おすすめ学習管理アプリURL: 【公式】スタディサプリ|大人の英語も、受験勉強も。
最新の入試情報はここから!:東京大学
🔰【前提】2年間の全体像と戦略方針
- まずは、1年目(高2)では基礎完成と習慣化を優先することが重要です。
- 一方で、2年目(高3)は演習と得点力の完成期と位置づけ、実戦的な訓練に移行します。
- 特に、共通テストで「情報Ⅰ」が必須化されたため、早い段階からの対策が必要です。
🕊️【高2春〜初夏(4〜6月)】基礎固めの第一歩
英語
- まずは、中学〜高1レベルの英文法と構文を総復習しておくと良い。
- 次に、音読とシャドーイングで長文の基礎的読解体力をつける。
- また、英単語帳(例:鉄壁、シス単)を1冊に絞って暗記開始。
数学
- 最初に、数学ⅠAⅡBの教科書レベルを完全に定着させる。
- 加えて、チャート式やFocus Goldで標準問題まで演習。
- ただし、解法暗記に頼らず、なぜその解法かを説明できるように。
国語(現代文・古文・漢文)
- 現代文は、評論と小説をそれぞれ毎週1題ずつ読み、要約練習。
- 古文単語・文法をまず1冊で基礎暗記。例:「ゴロゴ」「読んで見て覚える」。
- さらに、漢文の句法(再読文字・返読順など)を整理し始める。
理科(物理・化学・生物)
- 最初は、教科書の章末問題・基本例題を丁寧にこなす。
- そして、基本用語や計算の定義(モル・力学など)を正確に覚える。
- 特に物理は、感覚よりも「式の意味」に慣れることが大切。
情報Ⅰ(新教科)
- まずは、「情報Ⅰ」教科書の内容をざっくり読んで、範囲を理解。
- そのうえで、アルゴリズム・二進法・データ表現などの基本概念をYouTubeやオンライン教材で補完。
- さらに、プログラミング経験(Python等)も遊び感覚で触れておくとよい。
☀️【高2夏(7〜8月)】集中的な復習と差のつく教科の先取り
英語
- この時期は、長文問題(標準レベル)を毎日1題読みこむ習慣をつけたい。
- さらに、語彙・文法・精読・速読のバランスを意識する。
- その一方で、英文解釈(例:「ポレポレ」)を通して構文力を高める。
数学
- ここで、ⅡBの先取りを本格化させる。特に「数列・ベクトル」は東大頻出なので早めに。
- また、苦手分野を放置せず「一気に潰す」姿勢を忘れずに。
- そして、夏休みの1か月でチャート例題レベルの完答力を磨いておきたい。
理科
- 先取りを始めると同時に、「教科書の図・グラフの読み方」にも着目する。
- 加えて、実験系の用語や流れも覚え始めると後が楽になる。
- ただし、まだ演習よりも理解中心でOK。
情報
- 本格的に「情報Ⅰ」の問題集を1冊やり始める(例:スタディサプリ・Z会の基礎講座など)。
- さらに、模擬問題での演習を月に1〜2回こなすとペースがつかめる。
- 一方で、教科書を軽視せず、「理論分野」と「活用分野」の両方に目を通す。
🍁【高2秋〜冬(9〜12月)】アウトプット開始と過去問分析
英語
- まずは、模試や過去問(共通テストレベル)の長文に触れ始める。
- 次に、リスニング力を意識し、1日15分でも継続的に訓練。
- なお、東大の記述英作文対策もそろそろ視野に入れておく。
数学
- 過去問の「型」に慣れるため、全国難関大の記述模試などを活用。
- また、定期的に「時間を測って」答案を作成する訓練を導入。
- もちろん、わからなかった問題は「なぜミスしたか」の記録が必須。
理科
- 教科書内容を踏まえた演習問題に進む。セミナー・リードαなどの標準問題集がおすすめ。
- さらに、東大特有の「記述型」への意識を少しずつ持ち始めると良い。
- 一方で、記述練習はまだ週1〜2でよい。焦らず段階的に。
情報
- 共通テスト型の問題に取り組み始める(予想問題集を1冊解く)。
- そして、Pythonや疑似言語の流れをつかみ、変数や条件分岐を理解。
- 加えて、ICT活用や情報モラルなどの記述問題にも触れる。
高3春(3月〜6月):演習期への移行と得点力意識
- まずは、全教科において「得点を取る」視点を意識。
- 次に、共通テスト模試・記述模試の両方で弱点を炙り出す。
- 加えて、英語・数学・国語は「東大形式」に徐々に合わせていく。
夏(6〜8月):総合演習と記述力の鍛錬期
- いよいよ、東大過去問に本格的に取り組み始める。
- 一方で、共通テストの時間配分練習も定期的に実施する。
- 特に数学・国語は記述採点の精度向上が重要。
高3秋〜冬(9〜12月)実戦力の最終調整
- 本番と同じ時間割で過去問セット練習を行う(週1〜2回)。
- また、記述答案の「書き直し→添削→修正」サイクルを回す。
- さらに、情報や共通テスト系の最終仕上げも忘れずに。
年明け〜本番(1月〜2月):得点の最適化と体調管理
なお、過去問だけでなく「類題」も混ぜて出題パターンの変化に対応。共通テスト(1月中旬)に向け、センター形式の演習を集中実施。その後、東大2次に特化した記述力・時間配分の最終訓練を行う。
🚫東大合格が遠ざかるNG勉強法
〜「努力してるのに伸びない人」に共通する落とし穴〜
1. まずは「安心感を優先する勉強」から抜け出そう
- よくありがちなのが、簡単な問題ばかり解いて“やった感”を得ようとする勉強法。
- たとえば、青チャートの例題だけを繰り返して「解ける自分」に満足してしまうパターンです。
- しかしながら、実際の入試では初見の応用問題にどう対応するかが問われます。
- だからこそ、慣れた問題から脱却し、思考力を鍛える訓練が不可欠です。
2. 次に「計画倒れのスケジュール管理」は要注意
- 東大志望者の中には、完璧な計画を立てて満足してしまう人が少なくありません。
- ところが、実行できなければ意味がなく、むしろ「やれなかった自分」に自己嫌悪してモチベが下がります。
- そのため、計画は「7割実行できればOK」と思える柔軟性を持たせることが大切です。
- 加えて、毎週振り返って修正する習慣をつけると改善サイクルが回ります。
3. さらに「インプット偏重」は東大には通用しない
- 「ノートをきれいにまとめる」「参考書を読むだけ」など、頭に入った気になるだけの勉強は危険です。
- そもそも、東大の試験では「自分の言葉で説明できるか」「論理的に記述できるか」が問われます。
- ゆえに、インプットした内容はすぐにアウトプットする訓練が必須です。
- 問題を解きながら「なぜそうなるのか」を説明するクセをつけましょう。
4. また「他人の勉強法の丸パクリ」も非効率
- YouTubeやSNSで話題の勉強法に飛びつくのもよくあるミスです。
- たしかに、他人の成功体験は参考になりますが、それが自分に合うとは限りません。
- むしろ、自分の弱点や思考スタイルに合っていない勉強法は逆効果になることさえあります。
- したがって、「試して、合わなければ捨てる」くらいの姿勢が必要です。
5. 最後に「記述練習を避ける姿勢」は致命的
- 「まだ早いから…」と記述式の過去問や論述を後回しにするのは、非常にもったいないことです。
- なぜなら、東大の2次試験は全科目が記述型で、答えを導くプロセスが重要だからです。
- そのため、高2の終わりごろからは、記述練習に少しずつ慣れておくべきです。
- 早いうちに「書けない」「伝わらない」壁にぶつかっておくことで、本番までに修正できます。
✅まとめ:NG勉強法から脱却するには?
- まずは、「やってる気がする」勉強から卒業しよう。
- 次に、「結果を出すための実行力」を日々の中で養おう。
- そして、自分に合うスタイルを見つけ、他人の真似に溺れないこと。
- 最後に、記述を恐れず、アウトプット中心の勉強へと進化させることが、東大合格への王道です。
東大・勉強法Q&A
❓東大合格に必要な勉強時間はどれくらいですか?
結論から言えば、高2時点で1日3〜5時間、高3では5〜8時間が目安です。
とはいえ、時間だけを意識しても意味はありません。なぜなら、東大入試は「質の高い思考」と「記述力」が求められるため、集中して勉強することが重要だからです。
一方で、部活や学校行事と両立しながら進めるには、週単位の計画を立てて、無理のないリズムを作ることがポイントです。
❓英語はどのように2年間で仕上げればいいですか?
まずは文法と単語の徹底から始めましょう。
たとえば高2では『Vintage』『ターゲット1900』『英文解釈の技術70』などを使い、基礎的な文構造の理解と語彙の習得を目指します。
その後、徐々に長文読解・英作文・リスニングにステップアップします。
つまり、「読む→書く→聞く」の順に広げていくのが基本です。
しかしながら、東大英語は記述量が多く、論理的に自分の意見を述べる力が問われます。
したがって、Z会や学校の添削などを活用し、アウトプットの質を高める工夫も必要です。
❓数学はどこまで問題集をやれば足りますか?
基本的には、教科書+青チャート → 標準問題精講 → 1対1対応の演習 → 過去問というステップで進めていけば問題ありません。
ただし、「理解したつもり」で進んでしまうと後で苦労します。
一方で、東大数学は解法暗記では対応できない問題も多いため、本質理解と答案作成力の両方を鍛える必要があります。
たとえば、1問を30分以上かけてじっくり考え抜く練習も、高3夏以降には不可欠です。
❓国語対策は現代文・古文・漢文それぞれどう進めるべきですか?
まず、現代文は読解法を学ぶことから始めましょう。
出口シリーズなどで「論理展開の型」を理解することで、点数が安定しやすくなります。
一方で、古文と漢文は語彙と文法の暗記が先決です。
つまり、暗記を先に終わらせておけば、読解や記述演習に時間を回せます。
しかしながら、東大の国語は「書く力」が非常に重視されます。
したがって、過去問や模試の記述を通じて、自分の考えを論理的にまとめる練習が不可欠です。
❓理科・社会の選択科目はいつから本格的に始めるべきですか?
理社は高3から始めても間に合うという声もあります。
たしかに、短期間で得点を伸ばしやすい側面はあります。
しかしながら、東大入試は「暗記+論述+資料の読み取り力」が問われます。
したがって、高2のうちに教科書と資料集で基礎的な背景理解を始めておくと、圧倒的に有利です。
たとえば、週2回だけでも地理の地形や歴史の流れを読む時間を設けることで、高3での演習効率が格段に上がります。
❓過去問はいつから始めるのが理想ですか?
結論としては、高3の夏に1年分だけ解いてみて、秋以降に本格的に着手するのが理想です。
なぜなら、最初から過去問を大量にこなしても、「パターンに慣れる」だけで理解が追いつかない場合が多いからです。
一方で、早めに出題傾向を知っておくことで、「今何を勉強すべきか」が明確になるというメリットもあります。
つまり、「解く→分析→対策」というサイクルを高3秋から週1ペースで回すのが効果的です。
❓部活と東大受験を両立できますか?
もちろん可能です。
実際、多くの東大合格者が高2の秋〜冬まで部活を継続しています。
ただし、限られた時間の中で成果を出すには、計画性と優先順位のつけ方がカギです。
つまり、「今の時期に何をやるべきか」「短時間で最大効果を出すにはどうするか」を常に考えながら勉強する必要があります。
✅ まとめ|東大勉強は「戦略」と「継続」が鍵になる
東大合格を目指すうえで、最も重要なのは「自分に合った勉強法を、継続的に実践すること」です。
しかしながら、やみくもに勉強を続けても成果は出にくいのが現実です。
つまり、合格への最短ルートは「戦略的な計画」と「科目別・時期別の対策」を組み合わせることにあります。
本記事で紹介したように、英語・数学・国語・理社それぞれに最適な勉強法が存在し、さらに季節ごとに重点が変わっていきます。
一方で、勉強法は個人差があるものです。したがって、他人の方法をそのまま真似するのではなく、自分なりにカスタマイズしていく柔軟性も必要です。
最後に強調したいのは、東大合格は「才能」ではなく「準備」で決まるということ。
今日から2年間をどう使うかで、未来は確実に変わります。
この記事を参考に、あなた自身の「東大合格戦略」を立ててみてください。
東大の勉強法に正解はありません。しかし、努力の積み重ねだけは、確実に合格へとつながります。
👉 この記事をブックマークして、今後の参考書選びや学習計画にぜひ役立ててください!
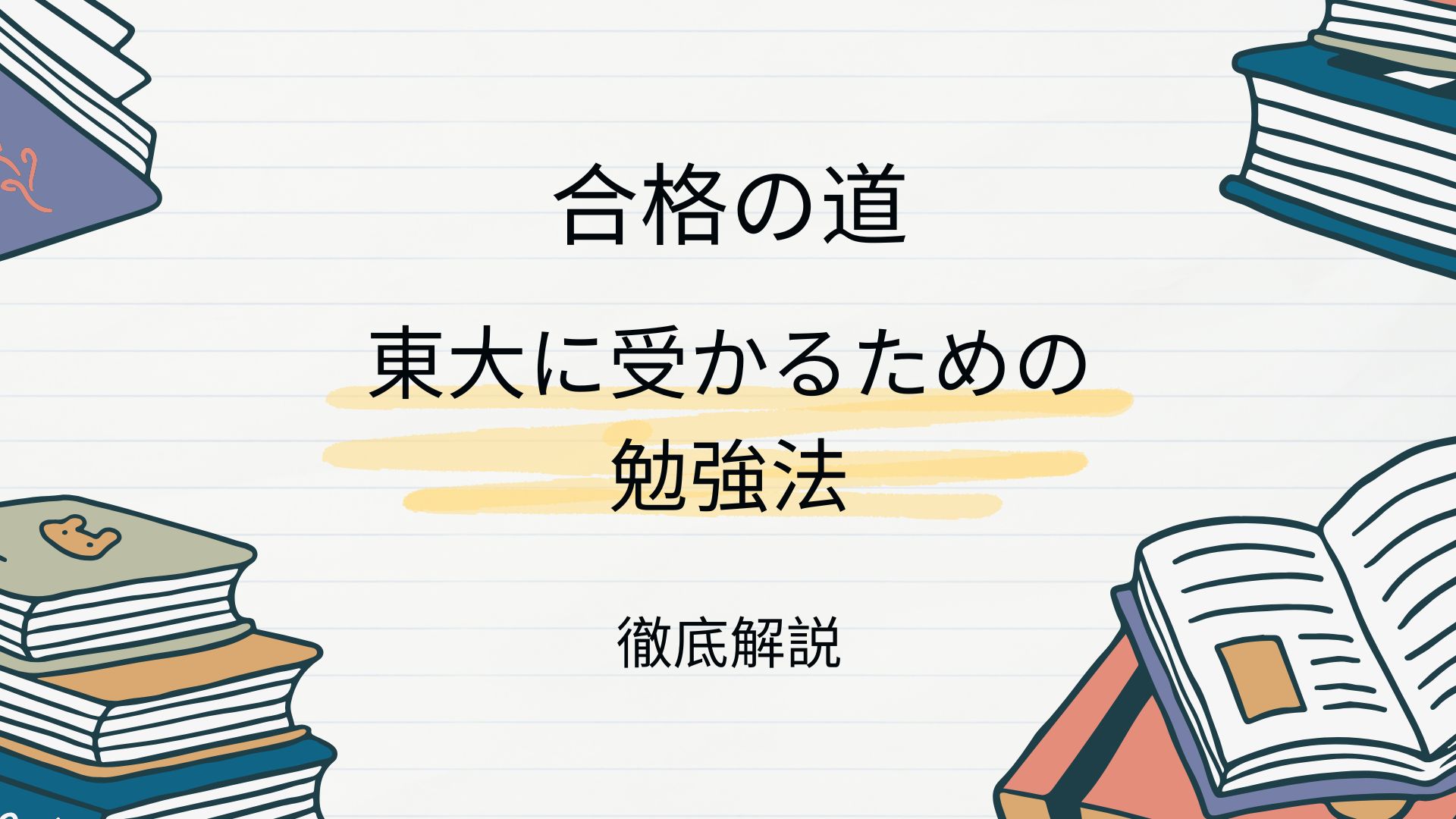
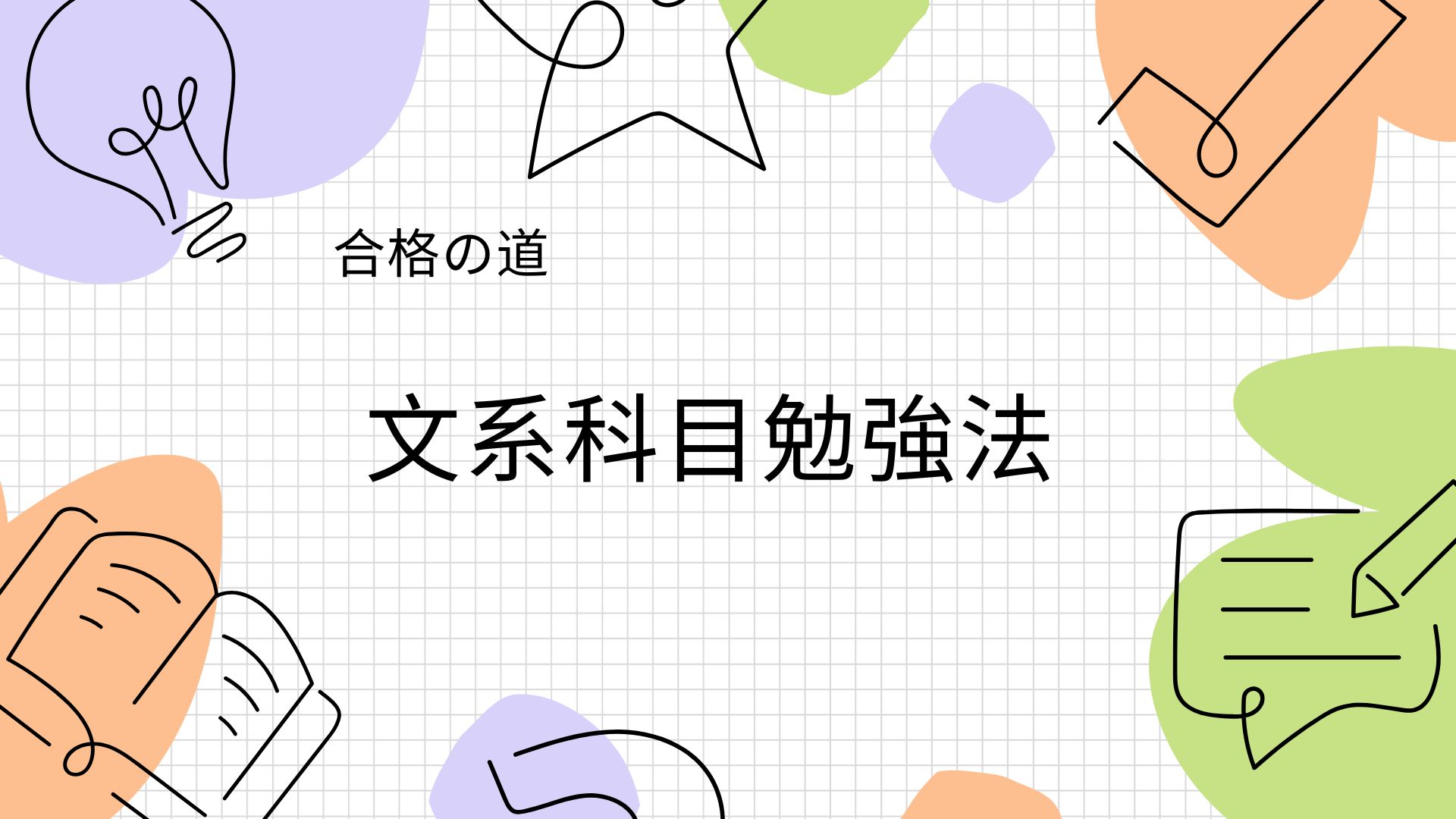
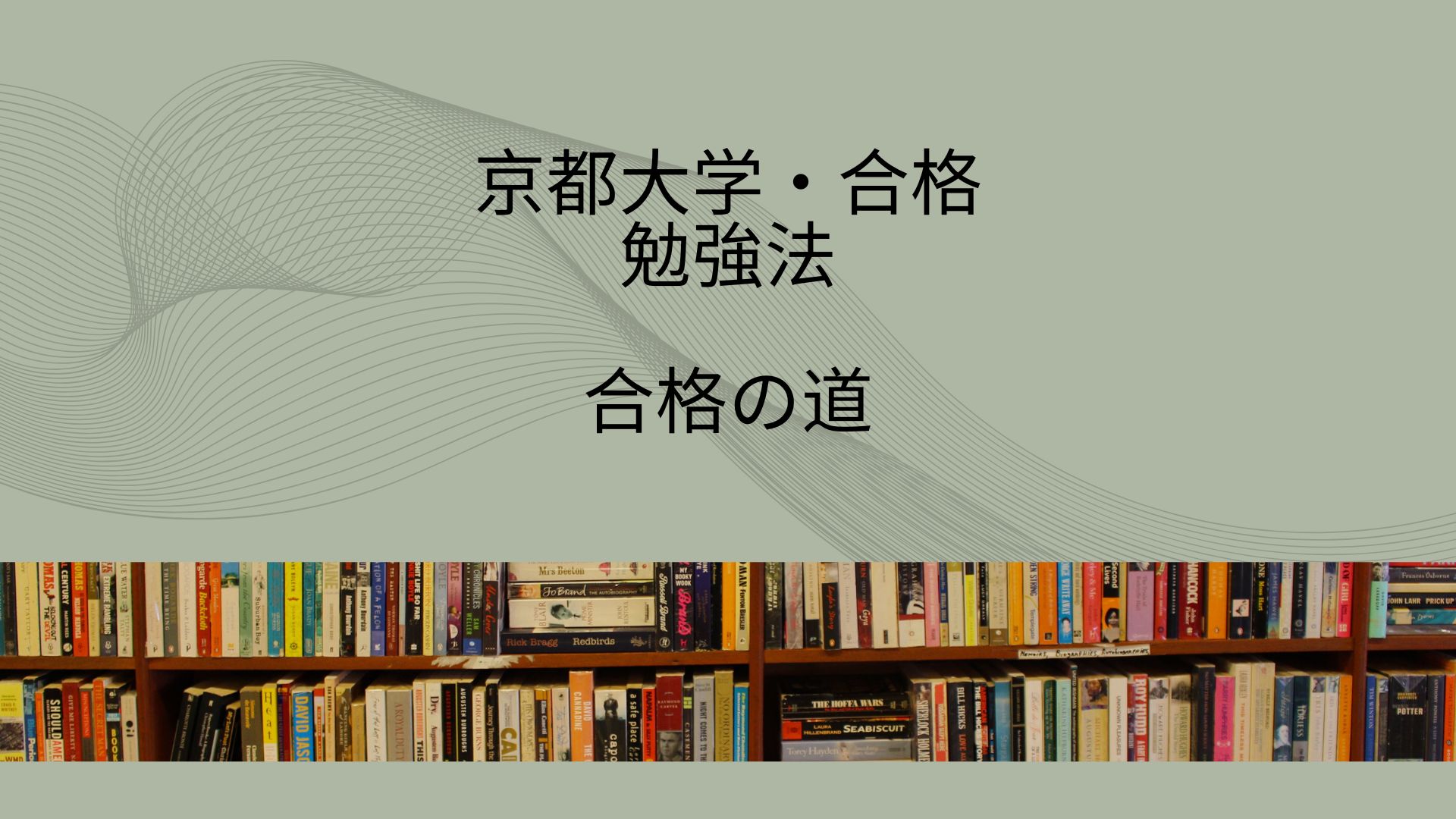
コメント